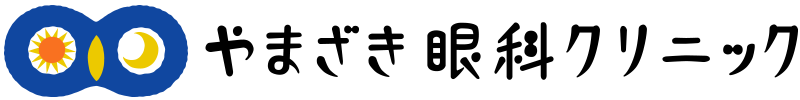逆さまつ毛
逆さまつ毛について
逆さまつ毛とは、まつ毛が正常な向きとは反対に内側(眼球側)へ向かって生えてしまう状態を指します。まつ毛が眼の表面(角膜や結膜)に触れることで、異物感や炎症を引き起こすことがあります。まつ毛が目の表面に当たって痛かったり、まつ毛の刺激により涙の分泌が増えて目ヤニが増える原因となる場合があります。軽度の場合は特に治療を必要としませんが、症状が強い場合は適切な治療が必要です。
逆さまつ毛の原因
逆さまつ毛(広義)は、「まつ毛が眼球に触れる状態の総称」であり、細かく分けていくと、睫毛乱生、睫毛内反、眼瞼内反が含まれます。
睫毛乱生(しょうもうらんせい)とは、まつ毛が異常な位置から生えてしまう状態で、まぶたの構造が正常でも、まつ毛自体の生え方に異常があるため、眼に接触します。例えば、本来まつ毛が生えないはずの場所(まぶたの裏側や不規則な位置)から生えてくることがあります。
睫毛内反(しょうもうないはん)とは、まつ毛が内側(眼球側)に向かって生えている状態です。まぶた自体の位置や形は正常ですが、まつ毛の生える向きに異常があり、角膜や結膜に接触します。乳幼児の下まぶたでよく見られる先天性のタイプが多いですが、成長とともに自然に治ることもあります。
眼瞼内反(がんけんないはん)とは、まぶた自体が内側(眼球側)に向いてしまい、その結果、まつ毛も眼に触れる状態です。 これは、まぶたの筋肉や皮膚の異常によって起こるもので、高齢者で多くみられる加齢性のものや、瘢痕性(手術後やケガの影響)のものがあります。
逆さまつ毛は年齢を問わず発症しますが、原因によって、以下のように分類できます。
1. 先天性(乳幼児に多い)
- 下まぶたの皮膚や筋肉の発達が未熟なため、まつ毛の生える方向が正常に定まらず、内向きになることがあります。睫毛内反となります。
- 成長とともにまぶたの構造が整うと、自然に治ることもあります。
2. 加齢性(高齢者に多い)
- まぶたの皮膚や筋肉が緩み、まつ毛が内側へ倒れ込むことで起こります。
- 皮膚のたるみによる「眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)」が原因となることが多い。
3. 瘢痕性(病気やケガが原因)
- 眼の手術後や結膜炎、外傷による瘢痕(傷あと)が原因で、まぶたの形が変わり、まつ毛の向きが内向きになることがあります。
逆さまつ毛の症状
まつ毛が眼に触れることで、以下のような症状が現れます。
異物感
ゴロゴロする、何か入っている感じがする
目の充血
慢性的な刺激により、目が赤くなる
涙が増える(流涙)
目の防御反応として涙が出やすくなる
痛み
特に、まつ毛が角膜に当たると痛みが出やすい
視力低下
長期間放置すると角膜に傷がつき、視力に影響を与えることがある。症状の程度はまつ毛の本数や角膜への接触範囲によって異なる。
逆さまつ毛の検査
眼科での診察により、まつ毛の向きや眼の状態を確認します。
細隙灯顕微鏡検査
(さいげきとうけんびきょうけんさ)
まつ毛がどの程度眼に触れているか、角膜や結膜に傷がないかを詳しく調べます。
眼瞼(まぶた)の診察
まぶたの位置や皮膚のたるみ具合を確認し、眼瞼内反症や瘢痕性変化がないかを評価します。
フルオレセイン染色試験
角膜の傷をより詳しく観察するため、特殊な染色液を使ってチェックします。傷があるところが蛍光色に光って細かな傷を発見しやすくなります。
逆さまつ毛の治療
軽度の場合
(まつ毛が少ない場合)
睫毛抜去(まつ毛を抜く)
- 眼に触れているまつ毛をピンセットのような道具で抜くことで、一時的に症状を改善します。
- ただし、数週間~1か月でまた生えてくるため、根本的な治療にはなりません。また、生え始めたまつ毛が眼球の表面にツンツンと当たる時に痛みが強く出ることがあるため、ある程度長く伸びて寝転んでいるまつ毛で、症状が強くなければ抜かずに経過をみることもあります。
点眼治療
- 角膜の傷を保護するために、目の表面を保護する目薬や炎症を抑える抗炎症点眼薬を使用します。
重度の場合
(まつ毛が多い、繰り返す場合)
手術(下眼瞼内反症)
- 埋没法
まぶた(下眼瞼)が内側に向いてしまう状態を改善するために行う手術です。局所麻酔を使用し、下まぶたに数か所小さな切れ目を入れ、糸を使ってまぶたの向きを外側に反らせることで、まつ毛が眼に当たらないようにします。この方法は皮膚を大きく切らないため、傷跡が目立ちにくく、回復も比較的早いのが特徴です。軽度~中等度の眼瞼内反症に対して行われます。 - 皮膚切開術
まぶたの皮膚を調整して、まつ毛が内側に入らないようにする手術。
瞼の手術は比較的負担の少ない手術ですが、いくつかの合併症が起こる可能性があります。手術後には、一時的に腫れや内出血が見られることがあり、特に術後数日間はまぶたがむくんだように感じることがあります。ただし、通常は1週間ほどで腫れは引き、自然に落ち着いていきます。また、ごくまれではありますが、手術部位に細菌が入ることで感染症が起こる可能性もあります。適切な処置を行えば大きな問題にはなりませんが、術後に赤みや痛みが強くなる場合は、早めの受診が重要です。手術後の違和感として、まぶたの内側に糸を感じることがあるものの、多くの場合は時間とともに気にならなくなります。
瞼の手術で注意すべき点のひとつに、再発の可能性があります。時間が経つとまぶたの筋肉や皮膚の張力が元に戻ってしまい、再び内反が生じることがあります。このため追加の手術が必要になることがあります。
生活上の注意点
目をこすらない
逆さまつ毛があると、異物感が強いため目をこすりたくなりますが、こすると角膜が傷つきやすくなります。
ドライアイのケアをする
目が乾燥すると刺激を感じやすくなるため、人工涙液などの点眼で目の潤いを保つことが大切です。
定期的に眼科を受診する
逆さまつ毛を放置すると角膜に傷ができやすく、視力低下につながることもあります。特に症状が繰り返す場合は、眼科で適切な治療を受けることが重要です。
鑑別疾患
逆さまつ毛と区別が必要な疾患
甲状腺眼症
(こうじょうせんがんしょう)
甲状腺眼症では、甲状腺機能異常(特にバセドウ病)によって眼球が前に押し出される(眼球突出)ため、まぶたが引き上げられ、逆さまつ毛のようにまつ毛が眼の表面に当たることがあります。これは一般的な逆さまつ毛の治療とは原因が異なるため、甲状腺の治療や眼球突出の治療が必要になる場合があります。
眼瞼痙攣(がんけんけいれん)
眼瞼痙攣とは、まぶたの筋肉が無意識に収縮し、異常な動きをする病気です。瞬きがうまくできず、ギュッと閉じた状態になってしまう病気です。(よく目のピクピクする疾患(眼瞼ミオキミア)と間違えられやすい病気です)重度になると、まぶたが内側に引き込まれることで逆さまつ毛のようにまつ毛が眼球に当たることがあります。ボツリヌス毒素(ボトックス)注射などで筋肉の動きを和らげる治療が行われることがあります。
眼瞼縁炎(がんけんえんえん)や慢性結膜炎
眼瞼縁炎(まぶたの縁の炎症)や慢性結膜炎があると、炎症によってまつ毛の生え方が乱れ、逆さまつ毛のような症状が出ることがあります。炎症が続くことで、まつ毛の向きが変わったり、まつ毛が抜けたりすることがあり、まつ毛が眼に当たることで異物感や痛みが生じます。これらの疾患では、炎症を抑える点眼薬や軟膏の治療が有効な場合があります。
まとめ
逆さまつ毛は、まつ毛が本来の向きとは異なり、内側に向かって生えることで眼の表面に刺激を与え、異物感や充血、痛みなどの症状を引き起こす疾患です。その原因には、先天的なまぶたの発達不良、加齢によるまぶたの変化、炎症や外傷による瘢痕性の変化など、さまざまな要因が関係しています。
軽度の逆さまつ毛であれば、まつ毛を抜いたり、点眼薬で症状を和らげることで対処できる場合もありますが、繰り返し発症したり、重度になると角膜に傷がつき、視力低下の原因となることがあります。その場合は、埋没法や皮膚切開術といった手術的治療が必要になることもあります。
日常生活では目をこすらないように注意し、ドライアイ対策として目の潤いを保つことも重要です。