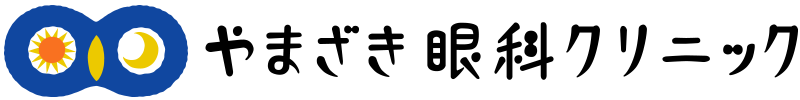甲状腺眼症(バセドウ眼症)
甲状腺眼症(バセドウ眼症)の原因
甲状腺眼症は、主にバセドウ病(Basedow病)に関連して発症する自己免疫性疾患です。甲状腺機能異常がある患者の約25~50%に発症するとされており、日本のデータでは、毎年10万人当たり、7人発症するとされています。男女比は偏っており、女性の罹患率は男性の3~4倍です。特に中年女性に多く見られ、40歳~60歳代の働き盛りの年齢に多い疾患です。
甲状腺眼症は、甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体に対する自己抗体(TRAb、TSAb)などが原因で眼窩の線維芽細胞が刺激され、炎症や組織の腫脹を引き起こします。これにより、眼球突出、眼瞼後退、眼球運動障害などの症状が現れます。眼球突出を来たす眼科疾患の中では最も頻度が高い疾患です。
バセドウ眼症の症状
甲状腺眼症の症状は多岐にわたり、以下のようなものがあります。
眼球突出
眼窩内の筋肉や脂肪が腫れることで、眼球が前方に押し出される。
眼瞼後退
上まぶたが引き上げられ、白目が露出しやすくなる。
複視(物が二重に見える)
外眼筋の炎症や線維化により、眼球の動きが制限される。
目の乾燥や異物感
涙の分泌が減少したり、眼球突出の影響で目が乾燥しやすくなる。
光過敏や視力低下
重症例では、視神経が圧迫され視力が低下することがある。
甲状腺眼症の活動性の評価には**Clinical Activity Score(CAS)**が用いられます。CASの合計が3点以上の場合、活動性が高いと判断されます。(日本人では、CAS 1~2点でもMRIで評価すると炎症所見を認めることがあります。)
CASの評価項目(各1点)
- 目の奥の痛みや違和感
- 上方・下方を見たときの痛み
- まぶたの赤み
- まぶたの腫れ
- 結膜の充血
- 結膜の浮腫(むくみ)
- 涙丘(目頭部分)の腫れや赤み
一般的に、甲状腺眼症の症状は朝方に強くなる傾向があります。
バセドウ眼症の検査
診断には以下の検査が行われます。
血液検査
- 甲状腺ホルモン(FT3、FT4、TSH)
- 甲状腺自己抗体(TRAb、TSAb、抗TPO抗体)
眼科的検査
- 眼球突出測定(Hertel眼球突出計)
この器械は、目の奥行きを測るための専用の定規のようなものです。目の横にある眼窩(がんか)という骨(目を囲む骨)を基準にして、角膜(黒目の中心のふくらみ)までの距離を測ります。日本人は10~15mm(平均13mm)が正常で、それ以上を眼球突出と判定します。左右差は2mm以内が正常であるとされています。 - 眼位・眼球運動の評価
目の位置や動きが正常かどうかを調べる検査です。眼位とは目の位置のことで、両目がまっすぐ向いているか、ズレていないかをチェックします。眼球運動の評価は目がスムーズに動くかどうかを調べることで、目には6つの筋肉が付着して目を動かしていますが、それぞれの筋肉が正常に動いているかを確認する検査を行います。
甲状腺眼症では、眼球の下と内側についている筋肉(下直筋、内直筋)が肥厚する場合が多いです。肥厚した筋肉が伸びにくくなるため、結果として目を上に向けたり外側に向けたりするのが難しくなる場合が多く、上方や側方に目線を向けると物が二重に見える場合があります。
画像検査
- CT/MRI:外眼筋や眼窩内の炎症・腫脹を確認
治療
治療は病状の進行度や症状に応じて選択されます。
1. 甲状腺機能のコントロール
内分泌内科医と連携し、甲状腺ホルモンのバランスを整え、甲状腺機能の正常化を図ることがまず重要です。
2. 薬物療法
副腎皮質ステロイド薬
全身あるいは局所の投与が行われます。全身投与としては、パルス療法として500~1000mg/日のステロイド薬の点滴を3日間行うのを1クールとして、病状に応じて数クール行い、その後ステロイド内服に切り替えて漸減していくケースが多いです。全身療法は入院で行われます。
局所療法としては、肥大した筋肉の周辺にステロイドの注射を行う方法や、瞼や瞼の裏側にステロイドの注射をする方法があります。ステロイド薬により眼圧上昇などの副作用が出る場合があるため、眼圧をモニタしながら加療を行います。
3. 放射線療法
軽症~中等症の患者で、ステロイド薬による治療が行えない場合や副腎皮質ステロイド薬治療後に再燃した場合に、眼球の後ろの組織に放射線照射が行われます。
4. 手術療法
眼窩減圧術
薬の治療に反応しない著明な眼球突出や圧迫による目の神経の障害がある場合に行われます。目の周囲にある眼窩の骨を削ることで目の収まっている眼窩の容積を拡大させる眼窩骨減圧術と、眼窩の脂肪を減量することで目の収まっている空間の混み具合を調整する眼窩脂肪減圧術があります。
斜視手術
複視が残存する場合に実施する場合があります。但し活動性の眼症がある場合には複視の程度が変化する可能性があるため、病勢がある程度落ち着いて症状が固定してから行われます。筋肉の肥厚によって筋肉が伸びにくくなっているため、原理的に全方向の複視を消失させることはできず、正面視の改善を目指します。
眼瞼手術
病勢の安定期に行われます。上眼瞼後退や眼瞼腫脹に対しては上眼瞼の手術や眼窩脂肪切除術が選択されます。下眼瞼内反症や下眼瞼下垂に対しては下眼瞼の手術が行われることがあります。甲状腺眼症の大きな問題の一つが眼球突出に伴う顔貌変化ですが、手術で完全に元通りにすることは困難であることから、強いドライアイを生じないように機能的な回復が目指されます。
5. テプロツムマブ(テッペーザ ®)
- 2024年に国内承認された新しい生物学的製剤で、活動性甲状腺眼症の治療薬です。点滴静注で3週ごとに計8回投与され、高額ですが保険診療の範囲内で治療可能です。副作用として聴覚障害のリスクがあるため、耳鼻科での聴力検査が必要になります。
- 眼球突出や炎症を軽減し、従来のステロイド治療に比べ糖尿病や高血圧、感染症のリスク増加といったステロイド薬特有の副作用がないため、近年注目されている治療選択肢の1つです。
生活上の注意点
甲状腺眼症の症状を悪化させないために、以下の点に気をつけましょう。
禁煙
喫煙は病気を悪化させるため、完全にやめることが大切です。
紫外線対策
サングラスや帽子を着用し、紫外線の刺激を避けましょう。
適切な睡眠
睡眠不足やストレスは症状を悪化させるため、十分な休息をとることが重要です。
目の乾燥対策
人工涙液を使用したり、加湿を心がけることで目の乾燥を防ぎましょう。
眼科・内科の定期受診
甲状腺のコントロールと眼の状態のチェックを定期的に行いましょう。
鑑別疾患
甲状腺眼症(バセドウ眼症)と区別が必要な疾患
眼窩蜂窩織炎
目の周りの組織への細菌感染によって生じます。鼻腔(目の近くにある空洞)の炎症である副鼻腔炎(ふくびくうえん)が悪化すると、その細菌が眼窩に広がってしまい、炎症を引き起こします。また、ケガをした部分から細菌が入り込んだり、虫刺されや歯の感染から広がることもあります。
IgG4関連疾患
免疫の異常によって眼の周りの組織が慢性的に腫れる病気です。涙腺や外眼筋、視神経周囲が腫れることが多く、眼球突出や複視を引き起こします。血液検査でIgG4の値が高くなることが特徴で、画像検査でも組織の腫れが確認されます。
頸動脈海綿静脈洞瘻
頸動脈と海綿静脈洞の間に異常な血流が生じる病気です。拍動性の眼球突出、結膜充血、眼球運動障害などが特徴で、外傷や動脈の異常によって発症します。診断にはMRIや血管造影が有用で、軽症なら自然閉鎖することもありますが、重症例では血管の治療が必要になります。
まとめ
甲状腺眼症は、主にバセドウ病に関連する自己免疫疾患で、眼球突出や複視、眼瞼後退などの症状を引き起こします。病気の活動性はClinical Activity Score(CAS)を用いて評価され、適切なタイミングで治療を開始することが重要です。治療法にはステロイド療法、放射線療法、眼窩減圧術、斜視手術などがあり、2024年に承認されたテプロツムマブは新たな選択肢として注目されています。治療は内分泌内科や眼科、耳鼻科など複数の診療科が連携して行うことが望ましく、甲状腺機能のコントロールも重要です。また、禁煙や紫外線対策、目の乾燥予防など日常生活での注意点も症状の管理に役立ちます。
- 日本甲状腺学会・日本内分泌学会編. 甲状腺眼症診療の手引き. メディカルレビュー社. 2020.
- 日本甲状腺学会・日本内分泌学会 臨床重要課題「バセドウ病悪性眼球突出症の診断基準と治療指針の作成」委員会. バセドウ病悪性眼球突出症(甲状腺眼症)の診断基準と治療指針2023(第3次案). 2023.