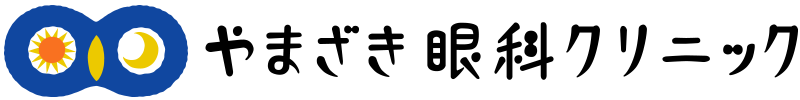ものもらい
(麦粒腫・霰粒腫)
ものもらい(麦粒腫・霰粒腫)の原因
ものもらいとは、まぶたの腫れや痛みを伴う疾患の総称であり、大きく「麦粒腫」と「霰粒腫」の2種類に分類されます。
麦粒腫(ばくりゅうしゅ)
まぶたの皮脂腺(マイボーム腺)や汗腺に細菌(主に黄色ブドウ球菌)が感染し、炎症を起こす急性化膿性疾患です。まつ毛の裏側や毛根に感染が生じています。
霰粒腫(さんりゅうしゅ)
マイボーム腺の分泌物が詰まり、慢性的な炎症を引き起こす疾患で、細菌感染は伴わないことが多いです。
ものもらいは全年齢層に発症しますが、特に10~40代の成人に多く見られます。また、コンタクトレンズの不適切な使用や目をこする習慣がある人は発症リスクが高まります。体力が低下している時や、糖尿病、免疫低下状態、慢性の眼瞼皮膚病がある場合に繰り返し起こることがあります。季節の変わり目、特に夏や春先に起こりやすい傾向がありますが、冬でも発症することがあります。
ものもらいの症状
ものもらいの症状は、麦粒腫と霰粒腫で異なります。
麦粒腫
- まぶたの赤み・腫れ・痛み
- まぶたの一部が膨らみ、化膿して膿がたまる
- まぶたの違和感や異物感
- 重症化すると発熱やリンパ節の腫れを伴うこともある
霰粒腫
- 無痛性のまぶたのしこり(腫瘤)
- 赤みや腫れを伴うことがあるが、痛みは少ない
- 大きくなると視界を妨げることがある
- 二次感染を起こすと麦粒腫のような痛みを伴う
ものもらいの検査
診断には以下の検査が行われます。
視診
腫れの部位、状態、炎症の有無を観察
細隙灯顕微鏡検査
まぶたの腫れやマイボーム腺の異常を詳細に確認
細菌培養検査
繰り返し発症する場合、抗菌薬の選択のために細菌の種類を特定
ものもらい(麦粒腫・霰粒腫)の治療
麦粒腫の治療
- 軽症の場合:抗菌点眼薬・抗菌眼軟膏(フルオロキノロン系、アミノグリコシド系など)
- 中等症以上:内服抗生剤(セフェム系、マクロライド系)を併用
- 膿がたまった場合:局所麻酔下で切開排膿
霰粒腫の治療
- 小さいもの:自然に吸収されることもあるため経過観察
- 温罨法(おんあんぽう):温めることでマイボーム腺の詰まりを改善
- ステロイド軟膏:炎症を抑える軟膏を1~2か月塗り徐々に吸収を促す
- ステロイド注射:大きくなった場合、炎症を抑えるために局所注射を行う
- 手術:視界を妨げるほど大きい場合や自然治癒しない場合には切開して摘出
温罨法(おんあんぽう)について
- ホットマスク(市販品)もしくは蒸しタオルを利用します。
- タオルを水で濡らし、電子レンジ(500~600W)で30~40秒加熱します。
- 熱すぎないか手で確認して、瞼の上に置く
- 5~10分間温める。(冷めたら交換する)
- 注意点:温めすぎに注意(45℃以上になると火傷や皮膚トラブルの原因になります)清潔な状態で実施(細菌感染を防ぐため、アイマスクやタオルは定期的に洗います)目の炎症がある場合には避ける(炎症が強い場合には温めることで余計に痛くなる場合があります)
- サウナの高温環境でもマイボーム腺の脂質を溶かしやすくなるため、一定の効果が期待できると考えます。但し、乾燥もしやすくなるのでドライアイには注意する必要があります。
生活上の注意点
甲状腺眼症の症状を悪化させないために、以下の点に気をつけましょう。
清潔保持
目をこすらない、コンタクトレンズの適切な管理
早期治療
症状が出たら温罨法や点眼の治療を行う。
再発予防
脂質の多い食事を避け、目元の清潔を保つ
コンタクトレンズの管理
レンズの清掃を徹底し、装着時間を守る
鑑別疾患
ものもらいと間違えられやすい疾患
眼瞼炎(がんけんえん)
眼瞼炎(がんけんえん)は、まぶたのふちが赤くなったり、かゆくなったりする病気です。細菌感染やアレルギー、まぶたの汚れが原因で炎症が起こり、目の周りに不快な症状が出ます。特に、まつ毛の根元にフケのようなものがたまったり、まぶたが腫れたりすることが特徴です。
「ものもらい」と比較して眼瞼炎は、腫れや赤みがあるものの、強いしこりができることはなく、目やにが増えたり、かゆみが出たりすることが多いです。治療には、まぶたを清潔に保ち、温めることが効果的です。症状がひどい場合は、眼科で目薬や軟膏を処方してもらうこともあります。日ごろから目をこすらないようにし、清潔を保つことが予防につながります。
眼瞼腫瘍(がんけんしゅよう)
眼瞼腫瘍(がんけんしゅよう)とは、まぶたにできる「できもの(腫瘍)」のことです。腫瘍には良性と悪性があり、良性のものは皮膚のできもののようにゆっくり成長し、痛みを伴わないことが多いですが、悪性の場合は次第に大きくなり、まぶたの形が変わったり、出血したりすることがあります。
眼瞼腫瘍は、見た目や症状が「ものもらい(麦粒腫)」や「霰粒腫」と似ているため、間違われることが多い病気です。ものもらいは細菌感染によって急にまぶたが腫れ、赤みや痛みが出ます。一方、霰粒腫はマイボーム腺の詰まりが原因で、徐々に硬いしこりができ、通常は痛みを伴いません。眼瞼腫瘍の場合、初期はこれらと似た症状を示しますが、長期間治らない場合や、しこりが次第に大きくなる場合は、腫瘍の可能性も考えられます。
特に注意が必要なのは、悪性腫瘍(がん)の場合です。眼瞼の悪性腫瘍には、基底細胞癌や脂腺癌などがあり、まぶたのただれや色の変化、しこりの拡大がみられます。これらは早期発見が重要なため、ものもらいだと思っていた腫れが長引く場合や、治療をしても改善しない場合は、眼科で詳しい検査を受けることが大切です。
結膜炎
目が赤くなったり、腫れたりすると、「ものもらいかな?」と思う人が多いですが、実は「結膜炎(けつまくえん)」の可能性もあります。どちらも目の病気ですが、原因や症状が違うので、しっかり区別することが大切です。
結膜炎とは、目の表面をおおっている「結膜(けつまく)」という薄い膜が炎症を起こす病気です。ウイルスや細菌が原因のものや、花粉やほこりなどのアレルギーが原因のものがあります。結膜炎になると、白目が赤くなり、涙がたくさん出たり、目やにが増えたりすることが特徴です。特にウイルス性の結膜炎は人にうつることがあるので、目をこすった手で物に触れないように気をつける必要があります。
一方、ものもらい(麦粒腫・ばくりゅうしゅ)は、まぶたにある脂を出す腺やまつ毛の毛穴に細菌が入って炎症を起こす病気です。ものもらいは、まぶたの一部が赤く腫れ、押すと痛みが出ることが特徴です。結膜炎のように目全体が赤くなるわけではなく、腫れる場所がピンポイントであることが多いです。さらに、ものもらいは目やにはあまり出ませんが、結膜炎は朝起きたときにまぶたがくっつくほど目やにが出ることがあります。
デルモイド嚢胞
まぶた(眼瞼)にできる良性の腫瘍の一つであり、皮膚や皮脂腺、毛髪などの成分を含む袋状の構造をしており、ゆっくりと成長する。特に眼瞼では、眉毛の近くやまぶたの外側にできることが多く、触れると弾力があり、通常は痛みを伴わない。
先天性の腫瘍であり、炎症がなければ赤みや痛みを伴わず、触れると比較的硬く滑らかである。デルモイド嚢胞は基本的に無害であるが、大きくなると見た目に影響を与えたり、眼球を圧迫したりすることがある。そのため、成長する場合や炎症を繰り返す場合には、手術による摘出が推奨される。嚢胞を完全に除去しないと再発する可能性があるため、適切な外科的処置が重要となる。霰粒腫と異なり、抗生剤や温罨法では改善しない。
まとめ
ものもらいは、まぶたの感染症や炎症によって引き起こされる疾患で、麦粒腫(ばくりゅうしゅ)と霰粒腫(さんりゅうしゅ)の2種類に分けられます。
麦粒腫は、まつ毛の毛穴やまぶたの脂を出す腺に細菌が感染することで起こる急性炎症です。まぶたの一部が赤く腫れ、強い痛みや熱感を伴います。数日で膿がたまり、最終的に自然に破れることもありますが、炎症がひどい場合は抗菌薬の使用や切開が必要になることもあります。
一方、霰粒腫は、まぶたの奥にあるマイボーム腺という脂を分泌する腺が詰まり、慢性的な炎症を起こす病気です。麦粒腫とは違い、痛みはほとんどなく、まぶたの中に硬いしこりができるのが特徴です。炎症がひどくなると赤く腫れることもありますが、基本的にはゆっくり大きくなります。軽症の場合は自然に治ることもありますが、長期間改善しない場合は温罨法(温める治療)や手術での摘出が必要になることがあります。
ものもらいを防ぐためには、目の清潔を保ち、むやみに触らないことが大切です。