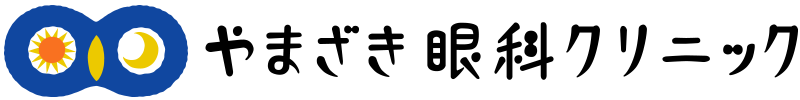斜視
斜視について
斜視(しゃし)とは、両目が同じ方向を向かず、片方の目が内側や外側、上や下を向いてしまう状態を指します。斜視のある人は、物を両目で同時に見ることが難しく、視力の発達に影響を与えることがあります。特に小児期に発症すると、弱視の原因となることがあるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
斜視の原因
斜視の発症頻度
- 斜視は国内では2~3%にみられる比較的よくある目の異常です。学齢期と高齢者で多い病気とされ、目の向く方向により、外斜視、内斜視、上斜視、下斜視、回旋斜視などとされています。
- 最も多いものは外斜視で、意識すると眼球が両眼ともまっすぐ向くときもある間欠性外斜視や常に外斜視が存在する恒常性外斜視に分類されます。学童期の間欠性外斜視は成長と共に軽快するもの、変わらないもの、徐々に恒常性となっていくものがあります。
- 成人になってから発症することもあり、これは脳卒中や神経障害などの病気が原因となることがあります。
斜視の原因
斜視は、眼球を動かす筋肉や神経の異常、視力のバランスの崩れによって発生します。
1. 先天性斜視
生まれつき目の動きを調整する神経や筋肉の異常があり、目の位置がずれてしまう。
2. 調節性内斜視
遠視が強いと、ピントを合わせようとする際に目が内側に寄ってしまい(内斜視)、視線がずれることがある。
3. 麻痺性斜視
外傷や脳卒中、神経の病気によって目を動かす神経が麻痺し、目の位置がずれる。
4. 加齢や外傷による斜視
成人になってから発症する斜視は、神経や筋肉の異常、外傷による眼球運動の障害が原因で起こることがある。
斜視の症状
斜視の症状は、目の位置のズレだけでなく、視力や日常生活にも影響を及ぼします。
- 目の位置がずれる(片目が内側・外側・上・下を向く)
- ものが二重に見える(複視)(後天性の斜視で多くみられます)
- 片方の目を使わなくなる(抑制)(子どもに多く、弱視の原因になる)
- 視界が不安定になり、距離感がつかみにくい
- 顔や首を傾ける癖がつく(斜視を補うために無意識に頭の角度を調整する)
特に、小児の斜視では、目のズレが目立たないこともありますが、片方の目を使わないことで視力の発達に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。また高齢者の斜視では、加齢によって脳の融像(ゆうぞう)の能力が低下し、両眼の画像をうまく処理できなくなることで物がぼやけたり、二重に見えたりすることがあります。
斜視の検査
斜視の診断には、目の動きや視力、両目のバランスを調べる検査を行います。
1. 視力検査
両目の視力を測定し、視力の発達に異常がないか確認します。
2. 眼位検査(カバー・アンカバーテスト)
遠くや近くに置いた指標を見た状態で一方の目を隠した際に、もう一方の目が動くかどうかを調べ、斜視の種類や程度を評価します。
3. 両眼視機能検査
ものを両目で同時に見る力(両眼視機能)を測定し、視線のズレがどの程度かを確認します。立体視の検査としてステレオテストが行われます。ステレオテストでは、専用の眼鏡をかけて、飛び出して見える絵をどこまで認識できるか調べる検査です。
4. 眼球運動検査
目の動きを調べます。麻痺性斜視が疑われる場合には、神経の異常を確認します。眼球の周囲には6つの筋肉がついており、上下左右、内旋、外旋を担っています。障害がある眼球運動の方向から問題のある筋を推定することができます。
5. 遠視検査(調節性斜視の評価)
遠視が原因で斜視が起こっているかどうかを調べます。子供は水晶体の柔軟性があり、ピントを調節できる範囲が非常に広いです。このため、子供の眼が一番リラックスした状態での遠視や近視の程度をチェックする目的で、調節麻痺剤を用いて屈折検査を行います。
治療
斜視の治療法は、斜視の種類や原因、年齢によって異なります。早期に治療を行うことで、視力や両眼視機能の発達を守ることができます。
1. メガネによる治療
調節性内斜視は遠視が強い子供に生じます。このため、通常の距離がその子にとってはすごく近くに感じられます。このため、近くのものを見る時に目が寄るように(輻輳)、目が中央によってしまいます。遠視を矯正するメガネをかけることで斜視が改善することがあり、眼鏡処方を行います。
2. アイパッチ療法
子供の視力発達には感受性期があります。適切な年齢までに目に適切な刺激が入力されないと脳が発達せず、大人になって眼鏡をかけても視力が1.0出ない状態となります。3歳児健診で視力を測定する目的の一つは治療を必要とする弱視の子を早く発見するためです。斜視が原因で片目を使わなくなることで視力が発達しない(弱視)のを防ぐため、アイパッチで良い方の目を一時的に覆い、弱い方の目の視力の発達をうながします。
3. プリズム眼鏡
複視(ものが二重に見える)がある場合、プリズムを入れた眼鏡を使用して、視線のズレを補正します。普段使っている眼鏡に貼るタイプのプリズム膜もあり、回復とともに眼鏡に貼りつける膜の度数を調節できるため、末梢循環障害などで生じる一時的な麻痺性の斜視の治療に有効です。
4. 斜視手術
目を動かす筋肉の長さや位置を調整し、目の向きを改善します。
5. ボツリヌス毒素注射
- 斜視の原因となる筋肉の動きを弱めます。
- 一時的な治療法だが、手術を避けたい場合に有効な場合があります。
生活上の注意点
斜視の症状を悪化させないために、以下の点に気をつけましょう。
- 小児の視力検査を視力の発達を確認できるまで行います。
- メガネやプリズム眼鏡を適切に使用します。特に弱視治療の眼鏡は視力が発達するまで毎日装用することが大切です。
- 成人発症の斜視では、脳や神経の病気が隠れていることあります。急な複視が生じた場合には、家で様子を見る時間がもったいないため、早めの病院受診をして下さい。
- 日常生活で目の疲れを軽減する工夫をする(パソコンやスマホの使用を適度に制限する)
鑑別疾患
斜視と区別が必要な疾患
偽斜視
偽斜視とは、実際には目がズレていないのに、斜視のように見える状態です。特に赤ちゃんや幼児では、鼻の付け根(鼻根部)が広かったり、目と目の間が近いと、内斜視のように見えることがあります。しかし、成長とともに鼻が高くなると自然に改善することが多いです。一方、本物の斜視は、片目が内側や外側、上や下にズレており、両目で同じ方向を見ることができない状態です。見分ける方法として、鼻根部をつまんで角膜の光の反射位置を確認する方法があります。もし鼻根部をつまんだときに、光の反射が中央にそろい、ズレがなくなれば偽斜視の可能性が高いです。
眼振
目が無意識に細かく揺れ動く状態で、自分の意思では止められません。一方、斜視(しゃし)は、片目が正しい方向を向かず、目の位置がズレてしまう状態です。眼振は視力の発達や神経の異常が原因で生じる場合があり、斜視とは異なる病気です。
脳卒中や神経麻痺による斜視様症状
突然の斜視は、脳卒中や動眼神経麻痺、重症筋無力症やFisher症候群などの神経筋結合部の全身疾患などの可能性があります。早期治療ができるかどうかで結果が大きく変わる病気が隠れていることがあるため、早めの受診が重要です。
甲状腺眼症
甲状腺機能異常により眼球が前に押し出され、視線のズレや複視を引き起こすことがあります。また、甲状腺眼症により、炎症を生じた目の周囲の筋肉が伸びにくくなり、目の動きが制限される場合があります。
まとめ
斜視は、片方の目が内側・外側・上下にズレてしまう状態で、特に小児では視力の発達に影響を与えるため早期の診断と治療が重要です。最も多いのは外斜視で、間欠性外斜視は学童期に見られ、成長とともに変化します。原因には先天的な要因や遠視、神経麻痺、加齢などがあり、症状として視界のズレや複視、距離感の障害が挙げられます。検査ではカバー・アンカバーテストや両眼視機能検査を行い、調節性斜視では屈折検査も実施します。治療はメガネやアイパッチ療法、プリズム眼鏡、ボツリヌス毒素注射、手術などがあり、早期の介入が視力の保護につながります。急な斜視は脳卒中や神経疾患の可能性があり、特に成人では迅速な診断が必要です。また、偽斜視や眼振、甲状腺眼症などと区別することが重要です。