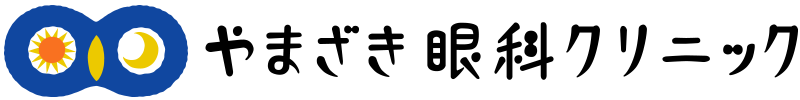眼瞼下垂(がんけんかすい)
眼瞼下垂(がんけんかすい)について
眼瞼下垂(がんけんかすい)とは、まぶた(上まぶた)が正常な位置よりも下がってしまい、目が開けづらくなる状態のことを指します。まぶたが垂れ下がることで視界が狭くなったり、額の筋肉を使って無理に目を開けようとするために疲れやすくなったりすることがあります。加齢に伴って起こることが多いですが、先天的なものや病気によって引き起こされることもあります。今回は、眼瞼下垂の原因や治療法、日常生活での注意点などについて詳しく解説します。
眼瞼下垂の発症頻度
眼瞼下垂は、年齢を重ねるにつれて発症しやすくなる病気であり、特に高齢者に多く見られます。しかし、生まれつきまぶたの筋肉が弱い人や、病気が原因で起こるケースもあり、全年齢層に発症の可能性があります。
眼瞼下垂の原因
眼瞼下垂の原因は、大きく 「先天性」と「後天性」 に分けられます。
先天性眼瞼下垂(生まれつきのもの)
- 眼瞼挙筋(がんけんきょきん)というまぶたを持ち上げる筋肉が未発達で、出生時からまぶたが下がっている状態。
- 片目だけでなく両目に発生することもあり、視力の発達に影響を与えることがあります。
- 視力の発達を妨げる場合には、早めに治療が必要になることもあります。
後天性眼瞼下垂(大人になってから発症するもの)
後天性眼瞼下垂にはさまざまな原因があり、以下のようなものが挙げられます。
加齢によるもの(腱膜性眼瞼下垂)
- 眼瞼挙筋腱膜(がんけんきょきんけんまく)のゆるみ
まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)は、腱膜(けんまく)と呼ばれる組織を介して、まぶたの骨や組織に付着しています。この腱膜が加齢によって緩んだり、伸びたりすることで、まぶたを十分に持ち上げることができなくなり、結果として眼瞼下垂を引き起こします。これは「腱膜性眼瞼下垂」と呼ばれるもので、加齢による眼瞼下垂の主な原因となります。軽度のうちは、額の筋肉(前頭筋)を使っておでこに皺を寄せて、目を開くことで補うことができますが、進行すると額の筋肉でも補いきれなくなり、視界が狭くなったり、目の疲れを感じたりするようになります。 - 皮膚のたるみ(眼瞼皮膚弛緩症)
加齢によるもう一つの変化として、まぶたの皮膚がたるんでしまうことが挙げられます。これは「眼瞼皮膚弛緩(がんけんひふしかん)」と呼ばれる状態で、皮膚の弾力が失われることで、まぶたが下がり、視界を遮る原因になります。 皮膚がたるむことで、まつ毛の上に皮膚が覆いかぶさるようになり、まぶたが重く感じることがあります。
眼瞼皮膚弛緩症が進行すると、眼瞼下垂と同じように視界が狭くなり、額の筋肉を使って目を開く動作が増えるため、頭痛や肩こりの原因になることもあります。 - 眼輪筋(がんりんきん)の衰え
目の周りには 眼輪筋(がんりんきん)という筋肉があり、この筋肉がまぶたの動きに関与しています。加齢によってこの眼輪筋の力が弱まると、まぶたを支える力が低下し、まぶたの位置が下がりやすくなります。 - 目の周りの脂肪の減少
加齢とともに、目の周囲にある脂肪が減少してしまうことも眼瞼下垂の原因の一つです。まぶたの脂肪が減ると、目の周囲の組織を支える力が弱まり、まぶたの構造が不安定になりやすくなります。眼窩脂肪(がんかしぼう)という目の奥にある脂肪が減ることで、まぶたが落ち込みやすくなります。逆に、脂肪が前に押し出されてしまう場合もあり、まぶたが腫れぼったくなることもあります。
コンタクトレンズの長期使用
コンタクトレンズの使用と眼瞼下垂の発症には深い関係があると考えられています。特に 長期間ハードコンタクトレンズ(HCL)を使用している人に眼瞼下垂が多い ことが知られています。コンタクトレンズによる眼瞼下垂の原因には「眼球の相対的な大きさの変化による負担」と「コンタクトの着脱動作による刺激」の両方の要因が関係していると考えられます。
病気や神経の異常によるもの
眼瞼下垂が、神経や筋肉の異常によって引き起こされる場合もあります。
外傷や手術後の影響
眼の手術後やケガの影響で、まぶたの筋肉が傷つき、下がってしまうことがあります。
眼瞼下垂の症状
眼瞼下垂の症状は、まぶたが下がることによる視界の問題や、目を開けようとすることによる疲労感が中心となります。
1. 視界の問題
- まぶたが下がることで視野が狭くなり、上の方が見えづらくなる。
- ひどい場合には、視界が大きく遮られ、視力が低下したように感じることもある。
2. 額や首への負担
- 目を開けようとする際に、額の筋肉を使ってまぶたを持ち上げるため、額にシワができやすくなる。
- 無意識にアゴを上げて物を見ようとするため、首や肩がこりやすくなる。
3. 目の疲れや頭痛
- おでこの筋肉を使って目を開けようとするため、眼精疲労が強くなる。
- まぶたが重く感じることで、集中力が落ち、頭痛を引き起こすこともある。
眼瞼下垂の検査
眼瞼下垂の診断には、以下のような検査を行います。
視診・問診
- まぶたの下がり具合や、目を開ける力を確認する。
- 額の筋肉を使って目を開けるかどうかをチェック。
視野検査
- まぶたの下がりが視界にどの程度影響しているかを確認。
眼瞼挙筋機能検査
- まぶたを持ち上げる筋肉の動きを調べ、神経や筋肉の異常がないかを確認。
血液検査・画像検査・電気生理的検査
- 眼瞼下垂が重症筋無力症や神経の病気によるものかどうかを調べるために、そのような原因を疑う場合に検査。
眼瞼下垂の治療
眼瞼下垂の治療には、手術による治療が基本となります。
手術療法
眼瞼挙筋腱膜前転術(けんまくぜんてんじゅつ)
まぶたを引き上げる筋肉である眼瞼挙筋がゆるんでしまった場合に行います。上まぶたを小さく切開し、伸びてしまった腱膜を元の位置に戻し、しっかり固定することで目を開けやすく調整します。
睫毛上皮膚切除術 (しょうもうじょうひふせつじょじゅつ)
まぶたの皮膚がたるんでしまい、まつ毛の上に覆いかぶさるようになってしまった場合に行われます。加齢によって皮膚が伸びると、視界が狭くなったり、まつ毛が眼に当たる違和感が出たりします。そこで、まつ毛のすぐ上の皮膚を切除することでまぶたの重さを取り除き、目の開きやすさを改善します。上記の眼瞼挙筋腱膜前転術と併用される場合も多いです。
眉毛下皮膚切除術
まぶたのたるみが強い場合に行われる手術です。加齢によってまぶたが重くなり、視界が狭くなった際に、眉毛の下の皮膚を切除することで余分な皮膚を取り除き、目を開きやすくします。特に皮膚のたるみが主な原因でまぶたが下がっている場合、耳側の目元に皮膚が覆いかぶさっている場合に適した方法とされています。
生活上の注意点
眼瞼下垂を予防するためには、日常生活の中でまぶたや目の周りの筋肉に負担をかけすぎないことが大切です。加齢による変化を完全に防ぐことはできませんが、生活習慣を見直すことで眼瞼下垂の進行を遅らせたり、発症を防いだりすることができます。以下に、日常生活でできる予防策を紹介します。
コンタクトレンズの使用時間を見直す
長期間ハードコンタクトレンズを使用すると、まぶたの筋肉や腱膜に負担がかかり、眼瞼下垂の原因となることがあります。コンタクトの着脱時にまぶたを頻繁に引っ張ることも影響します。眼瞼下垂を防ぐためには、コンタクトレンズと眼鏡を併用することが推奨されます。また、ソフトコンタクトレンズの方がまぶたへの負担が少ないため、ハードレンズを長年使用している人は、ソフトレンズへの切り替えを検討するのもよいでしょう。
目をこすらない
頻繁に目をこすると、まぶたの筋肉や腱膜が傷つき、伸びやすくなり、眼瞼下垂の原因となります。 目のかゆみがある場合は、抗アレルギー点眼薬を使う、冷やしてかゆみを和らげるなどの対策を取り、できるだけ目をこすらないように注意しましょう。
鑑別疾患
眼瞼下垂と区別が必要な疾患
重症筋無力症・Fisher症候群
重症筋無力症は、まぶたの下がりが時間帯によって変化するのが特徴です。朝や寝起きは調子良いのですが、疲れると徐々に下がってしまいます。全身の疲れやすさを伴うこともある疾患で、高齢者で増加しています。
Fisher症候群は風邪などの先行感染の後、典型的には2週間前後で発症します。物が二重に見えたり、ふらついたりする症状を伴う場合もあります。
動眼神経麻痺
まぶたが下がるだけでなく、眼球がうまく動かなくなることがあります。脳の血流障害や動脈瘤が原因となることがあり、その場合緊急対応が必要になります。
まとめ
眼瞼下垂は、視界の狭まりや疲労感を引き起こし、日常生活に影響を及ぼす疾患です。加齢とともに増加しています。治療の基本は手術となりますが、全身疾患の症状の1つである場合もあるため、適切な診断が重要です。