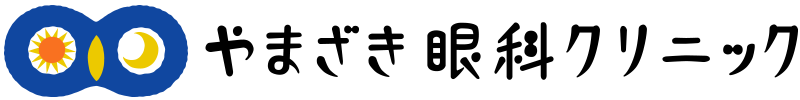翼状片(よくじょうへん)
翼状片(よくじょうへん)とは
翼状片(よくじょうへん)とは、白目(結膜)の一部が黒目(角膜)のほうに伸びてきてしまう病気のことです。特に外で過ごす時間が長い人に多く見られ、日差しが強い地域に住んでいる人や、紫外線をたくさん浴びる環境にいる人に発生しやすいです。
この病気は、中年から高齢の人に多く見られますが、若い人でも紫外線をたくさん浴びる生活をしていると発症することがあります。男女差はほとんどありませんが、特に屋外で働く人や、スポーツをする人は注意が必要です。また、乾燥した地域や砂ぼこりが多い場所に住んでいる人もリスクが高くなります。
翼状片として最も多いのが、結膜が鼻側から黒目に向かって伸びてくるパターンです。目の外側(耳側)にできることもありますが、頻度は低く、大半は鼻側から発生します。
翼状片の症状
翼状片ができると、次のような症状が現れることがあります。
- 目に違和感がある:目の表面に膜が伸びてくるので、ゴロゴロした感じがすることがあります。
- 目が赤くなる:翼状片の部分に炎症が起こると、目が充血して赤くなることがあります。
- 視力が落ちることがある:病変が黒目の中央に近づくと、角膜の形が変わってしまい、ものがぼやけて見えることがあります。乱視が強くなることで物が滲んで見えたり、多重に見えたりすることもあります。
- 目が乾く:涙のバランスが崩れてしまい、目が乾燥しやすくなることがあります。
翼状片の検査
翼状片があるかどうかを調べるには、眼科で次のような検査を行います。
目の表面を詳しく見る検査(細隙灯顕微鏡検査)
翼状片の形や広がり具合を確認します。眼球の乾燥に伴う眼の表面の傷も確認できます。
黒目の形を測る検査
(角膜トポグラフィー)
角膜がゆがんでいないか、不正乱視が出ていないかをチェックします。
視力検査
視力にどれくらい影響が出ているかを確認します。
涙の分泌量を測る検査
(Schirmer試験)
目の乾燥がどの程度あるかを調べます。
治療
翼状片の治療方法は、症状の重さによって変わります。
症状が軽い場合の治療
- 目薬(人工涙液)の使用:目の乾燥を防ぎ、不快感を和らげます。
- 炎症を抑える目薬(ステロイド点眼薬):炎症がひどいときに、一時的に使うことがあります。
- 紫外線対策:サングラスや帽子をかぶることで、病気の進行を抑えることができます。
進行した場合の治療(手術)
翼状片が大きくなって黒目に広がってきた場合は、手術をすることがあります。
翼状片の手術にはさまざまな方法がありますが、どの術式を選んだとしても、翼状片は再発しやすい病気であることが知られています。特に若い人ほど再発率が高くなる傾向があります。そのため、手術の際にはできるだけ再発しにくい方法を選ぶことが重要です。
今回は、翼状片の手術方法の一つである「ローテーション法」について説明します。
まず、局所麻酔を行ってから開始します。局所麻酔は目に点眼もしくは注射することで行い、手術中の痛みを感じないようにします。次に、角膜(黒目の部分)に癒着している翼状片の結膜を剥がします。その後、剥がした結膜の向きを変えて、元の位置とは異なる方向に回転(ローテーション)させ、縫合して固定します。
手術後には、いくつかの合併症が起こる可能性があります。例えば、手術直後には軽度の出血や浮腫(むくみ)が見られることがありますが、これらは通常、時間とともに落ち着きます。最も注意すべき点は、翼状片の再発です。どんな手術方法を用いたとしても、完全に再発を防ぐことは難しく、特に若い人では再発の可能性が高くなります。
また、非常にまれではありますが、手術後に癒着が強くなり、眼球の動きが制限されることがあります。このような場合には追加の治療が必要になることもあります。
生活上の注意点
翼状片を予防し、悪化を防ぐためには、次のようなことに気をつけましょう。
- 紫外線を避ける:屋外ではサングラスや帽子を活用しましょう。
- 目を乾燥させない:部屋の加湿や人工涙液の使用を心掛けましょう。
- 目をこすらない:目をこすることで、炎症が悪化することがあります。
鑑別疾患
翼状片と間違われやすい疾患
翼状片と似たような症状が出る病気には、次のようなものがあります。
偽翼状片(ぎよくじょうへん)
偽翼状片とは、翼状片に似た病気ですが、原因や特徴が異なります。翼状片は紫外線や乾燥、刺激などの影響で白目の膜(結膜)が角膜の上へ伸びてくる病気ですが、偽翼状片は目のケガや感染症、やけどなどが原因で発生します。
炎症が強い場合は目薬で炎症を抑えることが大切です。視力に影響が出たり、異物感が強い場合には、翼状片に準じて手術を行います。
結膜の腫瘍
翼状片と似たように見える病気の中には、結膜の腫瘍(できもの)も含まれます。特に注意が必要なのは、「脂腺癌(しせんがん)」や「扁平上皮癌(へんぺいじょうひがん)」という癌です。
翼状片との大きな違いは、広がり方や見た目です。翼状片は、白目(結膜)の一部が角膜の上に伸びてくる病気で、成長はゆっくりしています。表面はなめらかで、炎症があると赤くなることもあります。一方で、脂腺癌や扁平上皮癌は「びまん性」といって、じわじわと広がることが特徴です。表面がデコボコしていたり、出血しやすかったりすることがあります。
また、翼状片は紫外線や乾燥などが原因でできることが多いですが、脂腺癌や扁平上皮癌は、高齢の人に多く発生しやすいことが知られています。翼状片と思っていたものが、実は腫瘍だったというケースもあるため、疑わしい場合には切除した組織を顕微鏡で詳しく調べる「病理検査」という検査を行います。診断がつけば、全身への広がりを検査し、治療を行います。
再発翼状片
翼状片の手術を受けた後、再び同じように白目の膜(結膜)が角膜の上に伸びてくることがあります。これを「再発翼状片」といいます。一見すると翼状片と似ていますが、再発翼状片は翼状片とは異なる特徴を持ち、治療の考え方も変わります。
通常の翼状片は、白目の組織がゆっくりと角膜に伸びていく病気で、手術で切除することが可能です。しかし、再発翼状片は、一度手術を受けた後に組織が異常な形で修復され、強く角膜に癒着してしまうため、単純に切除するだけでは十分ではありません。特に、角膜の表面にしっかりと張りつくように広がり、場合によっては厚みを持つこともあります。
再発翼状片の治療は、初回の翼状片手術よりも難しくなることが多いです。なぜなら、手術による瘢痕(はんこん:傷跡)が強く残り、結膜や角膜と深く結びついてしまうからです。そのため、単に翼状片を切除するだけではなく、癒着した組織を慎重に剥がし、角膜の表面をできるだけ元の状態に近づけることが求められます。また、再発を防ぐために、結膜や羊膜(胎児を包む透明な膜)の移植や、特殊な薬剤を使って異常な細胞の増殖を抑える処置を行うこともあります。
まとめ
翼状片は、紫外線や乾燥、外的刺激などが原因となり、結膜が角膜へと伸びてくる病気です。軽症の場合は点眼薬や生活習慣の見直しで対処しますが、進行すると乱視が進行したり、目の表面を覆ってしまうことにより視力に影響を及ぼし、手術が必要になることがあります。特に若年者では再発しやすい傾向があります。翼状片の治療にはさまざまな方法がありますが、特に再発を防ぐためには適切な手術法の選択が必要になります。しかし、どんな治療法を選択しても完全に再発を防ぐことは難しく、定期的なチェックが大切です。
また、翼状片と似た疾患には偽翼状片や結膜の腫瘍があり、区別が難しいこともあるため疑わしい場合は細胞の検査が重要になります。日常生活では、紫外線対策、目の乾燥を防ぐことが翼状片の発症予防や進行抑制に役立ちます。