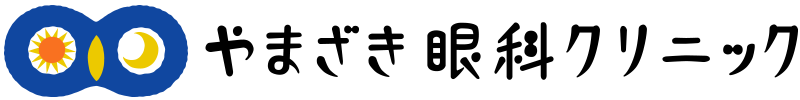アレルギー性結膜炎
(花粉症)
アレルギー性結膜炎
(花粉症)の原因
アレルギー性結膜炎は、目の表面にアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)が付着し、免疫反応によって炎症を起こす病気です。特に、花粉が原因で発症するものは「花粉症(季節性アレルギー性結膜炎)」と呼ばれます。
日本では、スギやヒノキ、ブタクサ、イネ科の花粉が主な原因となり、春や秋に発症する人が多いです。特にスギ花粉症は国民の約40%が罹患しているとされ、日本では非常に一般的な疾患です。また、通年性アレルギー性結膜炎は、ダニやハウスダスト、ペットの毛などが原因で、季節に関係なく症状が続きます。
アレルギー性結膜炎は全年齢層で発症しますが、特に若年層に多いとされています。小学生から20代にかけて発症率が高く、家族にアレルギー体質の人がいると発症しやすい傾向があります。
花粉症の症状
アレルギー性結膜炎の症状は、アレルゲンにさらされた直後から数時間以内に現れることが多いです。症状の強さは、アレルゲンの量や個人の体質によって異なります。
主な症状
- 目のかゆみ(最も特徴的な症状)
- 充血(白目が赤くなる)
- 異物感(ゴロゴロする)
- 涙目(流涙)
- 目やに(特に粘り気のある白っぽいものが出る)
- まぶたの腫れ
- 光がまぶしく感じる(羞明)
重症例では、かゆみが強すぎて目をこすりすぎることで、角膜(黒目の表面)を傷つけることがあります。また、アレルギー性結膜炎は両眼性(両目に症状が出る)であることが特徴です。
鑑別疾患
アレルギー性結膜炎(花粉症)と間違えられやすい疾患
1. ウイルス性結膜炎
ウイルス性結膜炎は、アデノウイルスなどのウイルス感染によって引き起こされる疾患です。アレルギー性結膜炎と異なり、感染性が高く、人から人へ感染する可能性があるため、特に注意が必要です。
症状の特徴としては、強い充血と大量の目やにがみられます。目やには黄色や緑色の膿のようなものが多く、朝起きるとまぶたが目やにで固まって開きにくくなることがあります。アレルギー性結膜炎では、目やには比較的少なく、粘り気のある白っぽいものが出る程度であるため、ここが大きな違いといえます。
発症の仕方にも違いがあります。ウイルス性結膜炎は片目から症状が始まり、数日後にもう片方の目にも広がることが多いです。一方、アレルギー性結膜炎は基本的に両目が同時に発症することが一般的です。この点も、診断の際の重要なポイントとなります。
また、ウイルス性結膜炎は非常に強い感染力を持つため、学校や職場で集団感染を引き起こすことがあります。特に、タオルや手で目を触った後に他のものに触れることでウイルスが広がりやすく、感染を防ぐためには手洗いやタオルの共用を避けることが重要です。アレルギー性結膜炎は、花粉やハウスダストなどのアレルゲンが原因であり、人から人へ感染することはありません。
2. 細菌性結膜炎
細菌性結膜炎は、ブドウ球菌や肺炎球菌などの細菌感染によって発症する結膜炎です。アレルギー性結膜炎とは異なり、細菌が直接目の表面で増殖し、炎症を引き起こすことが特徴です。感染力はウイルス性結膜炎ほど強くはありませんが、目をこすった手を介して他の人にうつることがあるため、注意が必要です。
症状の違いとして、目やにの量や性質が重要なポイントになります。細菌性結膜炎では、大量の目やにが出ることが特徴で、特に黄色や緑色の膿のような目やにがみられることが多いです。朝起きたときにまぶたが目やにで固まって開けにくくなることもあります。一方、アレルギー性結膜炎では、目やには比較的少なく、粘り気のある白っぽいものが出る程度であるため、ここが明確な違いになります。
また、充血の程度も異なります。細菌性結膜炎では、結膜の赤みが強く、まぶたの腫れを伴うこともあります。アレルギー性結膜炎でも充血はみられますが、かゆみが主な症状であるのに対し、細菌性結膜炎では痛みやゴロゴロとした異物感が強く出ることが多いです。
発症の仕方についても違いがあります。細菌性結膜炎は片目のみで発症することが多く、もう片方の目に広がることもありますが、必ずしも両目同時に発症するわけではありません。一方、アレルギー性結膜炎は最初から両目に症状が出ることが一般的です。
治療法にも違いがあります。細菌性結膜炎は細菌による感染症のため、抗菌点眼薬(抗生物質の目薬)で治療を行うことが基本です。適切な点眼をすれば数日で改善することが多いですが、重症化すると角膜(黒目の部分)に影響を及ぼし、視力低下につながることもあります。一方、アレルギー性結膜炎では抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬の点眼が使用され、原因であるアレルゲンの除去が重要となります。
細菌性結膜炎は、主に接触感染で広がるため、目をこすらないこと、こまめな手洗い、タオルの共用を避けることが予防につながります。アレルギー性結膜炎とは異なり、環境中の花粉やダニが原因ではなく、直接的な細菌の侵入が引き金となるため、衛生管理を徹底することが大切です。
3. ドライアイ
ドライアイは、涙の量が不足する、または涙の質が低下することによって目の表面が乾燥し、不快な症状を引き起こす疾患です。アレルギー性結膜炎とは異なり、免疫反応やアレルゲンの影響ではなく、涙の異常が主な原因となる点が特徴です。
ドライアイでは、目の乾燥感やゴロゴロとした異物感、目の疲れといった症状が現れます。アレルギー性結膜炎では強いかゆみが主な症状となりますが、ドライアイではかゆみはあまり強くなく、代わりに目がしみるような痛みを感じることがあります。特に、エアコンの効いた室内や長時間のパソコン作業などでは、症状が悪化しやすくなります。
また、アレルギー性結膜炎とドライアイは同時に発症することも多いため、単純にどちらか一方と判断するのが難しい場合もあります。アレルギー性結膜炎の治療に使用される抗アレルギー薬の点眼は、涙の分泌を抑えてしまうことがあり、その結果としてドライアイの症状が悪化することもあります。逆に、ドライアイが原因で目の表面が傷つくと、アレルゲンが入り込みやすくなり、アレルギー性結膜炎の発症を助長することもあります。
ドライアイの治療では、人工涙液(涙の代わりになる目薬)を使用して目の潤いを補うことが基本となります。アレルギー性結膜炎と異なり、炎症を抑える抗ヒスタミン薬やステロイドの点眼では根本的な改善にはならず、涙の分泌を促す治療が重要となります。予防策としては、加湿器を使用して室内の乾燥を防ぐ、まばたきを意識的に増やす、長時間のパソコン作業ではこまめに休憩を取ることが有効です。
アレルギー性結膜炎の検査
細隙灯顕微鏡検査
結膜の炎症や腫れ、眼表面の傷の有無を観察
眼脂(目やに)や涙の検査
好酸球というアレルギー反応の指標となる細胞を調べる
血液検査
IgE抗体の測定や特定のアレルゲンの特異的IgE検査
アレルギー性結膜炎の治療
薬物療法
アレルギー性結膜炎の治療では、アレルギー反応を抑える点眼薬が基本となります。
- 抗ヒスタミン薬点眼 → かゆみを素早く抑える効果がある
- メディエーター遊離抑制薬 → アレルギーの発症を予防する作用
- ステロイド点眼薬 → 症状の強い例に使用されます
- 免疫抑制薬 → 重症例に使用(特に春季カタルなどの重度のアレルギー性結膜炎に有効)
非薬物療法
- 冷罨法(れいあんぽう):冷たいタオルやアイスパックを目の上に当て、炎症を抑える
- 花粉の季節は外出を控える:特に花粉の飛散が多い日(晴れ・風の強い日)は注意
- メガネやゴーグルの着用:花粉が目に入るのを防ぐ
- 室内の換気を適度に行い、加湿器を使用する
生活上の注意点
アレルギー性結膜炎を予防し、症状を軽減するためには、以下の習慣が重要です。
- 目をこすらない:こすると角膜を傷つける可能性がある
- コンタクトレンズの適切な管理:できれば花粉症の時期は眼鏡を使用
- 帰宅後は洗顔やうがいを行う:目や顔についた花粉を落とす
- 布団やカーペットの掃除をこまめに行う:ハウスダストやダニを減らす
まとめ
アレルギー性結膜炎(花粉症)は、アレルゲンに対する免疫反応によって目のかゆみや充血を引き起こす疾患です。特にスギ花粉症は多くの人にみられ、春先に症状が悪化することが一般的です。診断には、問診と眼科的検査が中心となり、治療は抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の点眼を基本に行います。重症例ではステロイド点眼や免疫抑制薬が用いられることもあります。
生活習慣の改善も重要であり、花粉やアレルゲンの暴露を減らすことが予防の鍵となります。