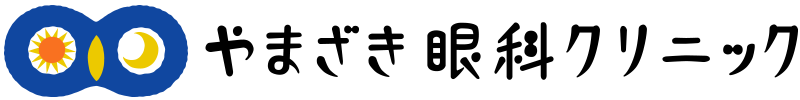緑内障
緑内障の原因
緑内障は、視神経が徐々にダメージを受けることで視野が狭くなっていく疾患です。初期には自覚症状がほとんどないため、気づいたときにはかなり進行していることが多い疾患です。 日本では、40歳以上の約20人に1人(5%)が緑内障を発症しているとされ、加齢とともに発症率が高まります。特に60歳以上では10%以上に達し、高齢者にとって非常に重要な疾患です。視野が一度失われると回復することはなく、早期発見・早期の治療介入が極めて重要です。
緑内障の発症には、眼圧(眼球内部の圧力)の上昇が関与していることが多いですが、眼圧が正常範囲内であっても発症する「正常眼圧緑内障」も多く、日本人に特に多いタイプとされています。その他、遺伝的要因や血流障害なども関係していると考えられています。
緑内障の症状
緑内障の特徴的な症状は、視野が徐々に欠けていくことですが、初期段階では気づきにくいのが問題です。
| 初期 | 視野の一部がわずかに欠けるが、両目で補い合うため自覚症状はほぼなし |
|---|---|
| 中期 | 視野の一部が明らかに狭くなるが、中心視野は保たれるため、日常生活に大きな支障はない |
| 進行期 | 視野が大きく欠損し、歩行時の障害(ぶつかる、段差につまずく)や、車の運転に支障を感じるようになる |
| 末期 | 視野が極端に狭まり、最終的には失明に至ることもある |
多くの患者が見えにくさを感じるのは病気が進行してからのため、定期的な眼科検診で早期発見することが大切とされています。人間ドックでも眼底写真を撮影し、眼科疾患を早めに見つけ出す動きが出てきています。
緑内障の検査
緑内障の診断には、以下のような検査を行います。
| 眼圧検査 | 眼圧が高いかどうかを調べる(ただし、日本人には眼圧が正常な「正常眼圧緑内障」も多い) |
|---|---|
| 視野検査 | 見える範囲を調べ、視野の欠損がないかを確認 |
| 眼底検査 | 視神経乳頭の状態を観察し、視神経の損傷を評価 |
| 光干渉断層計(OCT) | 視神経の厚みを測定し、早期の変化を検出 |
これらの検査を組み合わせることで、緑内障の診断を行います。光干渉断層計の検査では、視野欠損が出る前に網膜が薄くなっている箇所が明らかとなり、視野障害が生じる前の状態(前視野緑内障)という状態で目の病気を発見できるようになりました。また、視野検査では自覚症状がなくても欠損が確認されることがあり、こちらも早期発見に役立っています。
緑内障の治療
緑内障の治療の目的は進行を遅らせ、失明を防ぐことです。現在の医学では、一度失われた視野を回復させることはできないため、治療は眼圧を下げることを基本とします。
緑内障点眼薬による治療
点眼薬は緑内障治療の第一選択肢となります。主に以下のタイプがあります。
- プロスタグランジン関連薬
→眼圧を下げる効果が強く、1日1回の点眼で済むことが多い。
長期の利用で虹彩の色素沈着やまつ毛の変化、まぶたのくぼみが深くなるなどの副作用が出る場合があるため、洗顔前や入浴前に点眼される場合が多いです。 - β遮断薬
→房水(眼内の液体)の産生を抑えて眼圧を下げる。
交感神経の働きを抑えるため、気管支喘息や重度の心不全がある場合には利用できません。眼圧を下げる効果が強い目薬の一つです。 - 炭酸脱水酵素阻害薬
→房水の産生を抑え、眼圧を下げる - α2作動薬
→房水の排出を促しつつ、産生を抑える - Rhoキナーゼ阻害薬
→房水の流出路に働きかけて、眼内の水が排出されやすくして眼圧を下げる
患者の症状や副作用の有無に応じて、これらを単独または併用して使用します。目薬によってアレルギーを生じる場合もありますが、何種類も点眼の選択肢があるため、目に合う目薬を試していくことができます。
レーザー治療(SLT)
SLT(選択的レーザー線維柱帯形成術)とは?
SLT(Selective Laser Trabeculoplasty)は、緑内障の眼圧を下げるために行うレーザー治療です。線維柱帯(房水の出口)にレーザーを照射し、房水の流れを改善することで眼圧を下げます。
SLTの特徴
- 手術と比べて低侵襲
(治療の体への負担が少ない) - 点眼治療と併用できる
- 眼圧の低下効果は数年持続するが、再治療が可能
SLTは目薬の効果が不十分な場合や、目薬の副作用が気になる場合の選択肢となります。点眼薬を減らしたい場合にもメリットがあります。ただし、繊維柱帯が観察できない、閉塞隅角緑内障や繊維柱帯が損傷している場合、色素が沈着している場合など治療の適応とならない場合もあります。
白内障手術と緑内障
白内障がある場合、白内障手術によって眼圧が下がることがあります。そのため、白内障と緑内障が併存する場合は、白内障手術を行うことで緑内障の管理がしやすくなることがあります。
また、白内障手術と同時に「MIGS(低侵襲緑内障手術)」と呼ばれる緑内障手術を行うこともあり、白内障手術を機に緑内障の治療を進めることが可能です。
緑内障の手術
点眼薬やレーザー治療で十分な効果が得られない場合、手術を行うことがあります。
- 線維柱帯切除術(トラベクレクトミー):房水の排出路を新しく作る手術
- 線維柱帯切開術(トラベクロトミー):房水の流れを改善するために線維柱帯を切開
- チューブシャント手術:特殊な管を挿入し、房水の排出を助ける
手術はあくまで最後の手段として行われますが、進行した緑内障では有効な治療法となります。
生活上の注意点
緑内障の進行を抑えるためには、日常生活での管理も重要です。
- 点眼薬を正しく使用する(決められた時間に忘れずに点眼)
- 定期的に眼科検診を受ける(早期発見・経過観察が大切)
- ストレスを避け、適度な運動を心がける(血流を改善)
- 喫煙や過度の飲酒を控える(血流障害を防ぐ)
鑑別疾患
緑内障と間違われやすい疾患
視神経低形成
視神経低形成(Optic Nerve Hypoplasia, ONH)は、視神経の発育が生まれつき不完全である疾患です。視神経の本数が通常より少ないため、視野異常や視力低下がみられることがあります。一方、緑内障は視神経が加齢や眼圧の影響によって徐々に損傷し、視野が狭くなっていく病気です。両者とも視野異常を伴うため、誤診されることがありますが、いくつかの明確な違いがあります。
視神経低形成は、先天性の疾患であり、進行しないのが特徴です。出生後にすでに視神経が小さく形成されており、基本的に悪化することはありません。一方、緑内障は進行性の疾患であり、適切な治療をしなければ視神経のダメージが拡大し、視野欠損が進んでいきます。そのため、視神経低形成では視神経の変化が長期間変わらないのに対し、緑内障では経時的な悪化がみられることが大きな違いです。
視野の特徴にも違いがあります。視神経低形成では、視野の欠損パターンが不規則で、個人差が大きいのに対し、緑内障では典型的な弓状暗点や視野の鼻側欠損がみられることが多いです。
虚血性視神経症
視神経の血流が悪くなることで視力が急に低下する病気です。一方、緑内障は、眼圧が上がったり血流が低下したりすることで視神経がゆっくりとダメージを受け、視野が徐々に狭くなっていく病気です。この二つはどちらも視神経の異常を引き起こしますが、発症の仕方や症状に大きな違いがあります。
虚血性視神経症の特徴は、数時間から数日で急に視力が落ちることです。特に下の方の視野が見えにくくなることが多く、視神経が腫れるため、眼底検査で浮腫(むくみ)が見られることが多いです。一方、緑内障はゆっくり進行し、最初は自覚症状がほとんどありません。視神経が次第にへこみ、視野の外側から見えにくくなることが特徴です。 また、虚血性視神経症は、高血圧や糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病と関係が深く、緑内障は遺伝や加齢、近視が関係しています。
まとめ
緑内障は、日本の40歳以上の20人に1人が発症する疾患であり、早期発見・早期治療が重要です。眼圧が高いなどの原因で視神経が徐々に障害され、対応する箇所の視野が欠けていく病気ですが、眼圧を下げることで進行にブレーキをかけることができます。点眼薬、レーザー治療(SLT)、白内障手術、緑内障手術など、たくさんの治療選択肢があり、現在も新しい治療の研究が進められている分野です。定期的な検査と適切な治療により、進行を防ぎ、視力を守ることが可能です。