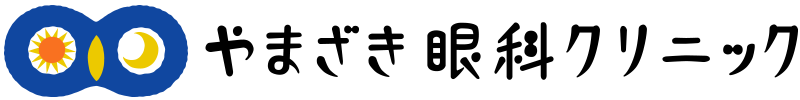ドライアイ
ドライアイについて
ドライアイは、目の表面を潤す涙の量が減ったり、涙の質が悪くなったりすることで、目の乾燥や不快感を引き起こす疾患です。日本では成人の約2割がドライアイを患っているとされ、特にパソコンやスマートフォンの使用が多い人に増加傾向があります。目が乾燥すると、視界がかすんだり、疲れやすくなったり、結膜下出血を生じることがあるため、適切な治療と日常生活でのケアが重要になります。
ドライアイの原因
ドライアイの発症頻度
(疫学)
- 日本人の約5人に1人がドライアイの可能性があるといわれています。
- 女性に多い傾向があります。
- 40歳以上の中高年に多いが、若年層でもパソコン・スマートフォンの使用増加により増えている。
ドライアイの主な原因
ドライアイは、大きく分けて「涙の量が減るタイプ」と「涙が蒸発しやすいタイプ」に分類されます。
涙の量が減るタイプ
(涙液分泌減少型)
- 加齢:年齢とともに涙の分泌が低下。
- シェーグレン症候群:自己免疫疾患の影響で涙腺が障害される病気。ドライアイ、ドライマウスが特徴的で、涙が分泌されにくくなる。
- 薬の副作用:抗うつ薬、抗アレルギー薬、降圧薬などが涙の分泌を減らすことがある。
涙が蒸発しやすいタイプ
(蒸発亢進型)
- パソコンやスマホの使用:まばたきの回数が減り、涙が蒸発しやすくなる。
- エアコンや乾燥した環境:空気が乾燥すると、涙が蒸発しやすくなる。
- マイボーム腺機能不全(MGD):まぶたの脂の分泌が悪くなり、涙の蒸発を防ぐ油分が不足する。
ドライアイの症状
ドライアイの症状はさまざまですが、以下のような特徴があります。
- 目が乾燥する(ゴロゴロする、しみる)
- 目が疲れやすい(特に長時間の作業後)
- 視界がかすむ(瞬きをすると少し改善する)
- 異物感がある(砂やホコリが入っているような感じ)
- 目が赤くなる(炎症を起こしやすい)
- 涙が異常に出ることがある(反射的に涙が出るが、すぐに乾いてしまう)
- コンタクトレンズがつけにくい、異常に乾く
- 目の痛みやヒリヒリ感
- まぶしさを感じる(光がまぶしい)
症状は軽い違和感から、視力低下を伴う重度の炎症まで幅広く、個人差があります。
ドライアイの検査
ドライアイの診断には、以下のような検査を行います。
1. シルマー試験
(涙液分泌量を測る検査)
- 目に検査用紙を挟み、5分間でどれくらい涙が染み込むかを測定する。
- 涙が少ないほどドライアイの可能性が高い。
2. BUT(涙液破壊時間)検査
- 目に蛍光色素を入れ、まばたきをした後、涙が蒸発するまでの秒数(BUT: Break-Up Time)を測定する。通常は10秒以上だが、ドライアイでは5秒以下になることが多い。
3. フルオレセイン染色試験
(角膜の傷をチェック)
- 特殊な色素を目に入れて、創の部分を強調することで角膜に傷がないかを調べる。
- ドライアイが進行すると、角膜に細かな傷がつくことがある。
治療
1. 点眼薬による治療
- 人工涙液:水分補給のための目薬
- ヒアルロン酸点眼:涙の保湿を助ける
- ジクアホソルナトリウム(ジクアス®)・レバミピド(ムコスタ®):涙の分泌を促進する点眼薬。
2. 生活習慣の改善
- まばたきを意識的に増やす。
- エアコンの風を直接目に当てない。
- 加湿器を使用する。
- コンタクトレンズを見直す(眼鏡と併用する)。
3. 涙点プラグ
- 上下の眼頭の部分にある涙の排出口(涙点)にシリコン製のプラグを挿入し、涙の流出を防ぐ。(中等度~重度のドライアイに有効です)
4. マイボーム腺のケア
- まぶたの脂分泌が悪い場合、温罨法(40℃程度の蒸しタオルを当てる)で改善することがある。
5. その他
- 顔面神経麻痺によって目が閉じられなくなると、常に眼球の一部が目にさらされていて充血が収まらない兎眼という状態となります。重症のドライアイです。他には、目薬のアレルギーのために従来の治療が行えない場合があります。その場合には、蒸発しにくい眼軟膏やソフトコンタクトレンズの利用、自己血清点眼、さらに視力がない場合には痛みを取る目的で上下眼瞼縫合術が行われる場合があります。一口にドライアイといっても原因や重症度が様々であり、多くの治療選択肢が提案されています。
生活上の注意点
ドライアイの症状を悪化させないために、以下の点に気をつけましょう。
- パソコンやスマホの使用時は、意識的にまばたきを増やす。
- 室内の湿度を50%以上に保つ(加湿器を使用)。
- エアコンの風を直接目に当てない。
- コンタクトレンズの装用時間を短くする(眼鏡との併用が望ましい)。
- ホットアイマスクや蒸しタオルを使い、まぶたの血流を改善する。
- 目をこすらない(角膜に傷がつく原因になる)。
- バランスの良い食事をとる(オメガ3脂肪酸が涙の質を改善するとされています)。
鑑別疾患
ドライアイと区別が必要な疾患
1. シェーグレン症候群
免疫の異常によって涙や唾液が出にくくなる病気で、特に中高年の女性に多くみられます。この病気になると、目が乾いてゴロゴロしたり、口の中が乾いて食べ物が飲み込みにくくなったりすることがあります。ドライアイやドライマウスが代表的な症状ですが、関節の痛みや疲れやすさが出ることもあります。診断には血液検査を行い、免疫の異常があるかを調べるほか、涙や唾液の分泌量を測定することもあります。根本的な治療法はありませんが、目薬や人工唾液などで症状を和らげる治療が行われます。
2. 眼類天疱瘡
(がんるいてんぽうそう)
免疫の異常によって結膜(白目の表面の膜)や角膜に炎症が起こり、まぶたや白目が癒着してしまう病気です。進行すると、結膜が癒着して偽膜(はがれにくい膜)ができたり、角膜が傷ついて視力が低下することもあります。診断には血液検査で特定の自己抗体を調べることが有効な場合があります。治療としては、炎症を抑える点眼薬やステロイドの内服薬を使用し、進行を抑えることが重要です。
3. 顔面神経麻痺
(がんめんしんけいまひ)
顔面神経麻痺では、まぶたを閉じる筋肉がうまく動かせなくなり、目が完全に閉じられなくなることがあります。この状態を「兎眼(とがん)」といい、寝ているときも目が少し開いたままになることがあります。まぶたが閉じられないと涙が蒸発しやすくなり、目が乾いてしまう(ドライアイ)ため、ゴロゴロしたり、痛みを感じたりすることがあります。治療としては、人工涙液の点眼や、夜間に眼軟膏を塗ることで目の乾燥を防ぎます。重症の場合は、まぶたが閉じやすくなるような手術を行うこともあります。
4. その他
強度近視や甲状腺眼症もドライアイとの関連が指摘されています。強度近視の人は眼球が他の人と比較して大きいため、空気に触れる面積が大きく、蒸発しやすくなります。また角膜の形状やコンタクトレンズの利用、近くのものを長時間見続けることが多い傾向があることから、まばたきの回数が減る傾向にあります。 甲状腺眼症でも、眼球突出により眼球が空気に触れる面積が増えるため、涙が蒸発しやすくなります。意識的にまばたきを増やしたり、目薬を利用するなど症状を緩和する治療が有効と考えられています。
まとめ
ドライアイは、涙の量が減ったり、涙の質が悪くなったりすることで目が乾燥し、不快感を引き起こす疾患です。日本では成人の約5人に1人がドライアイとされ、特にパソコンやスマートフォンを長時間使用する人に増加傾向があります。原因には加齢やシェーグレン症候群などの疾患、コンタクトレンズの使用、まばたきの減少、エアコンによる乾燥などがあり、涙の分泌が減るタイプと蒸発しやすいタイプに分けられます。症状として、目の乾燥感やゴロゴロする異物感、視界のかすみ、目の疲れ、まぶしさを感じることなどが挙げられます。
診断には、涙の量を測るシルマー試験や涙の蒸発時間を調べるBUT検査などが用いられます。治療には、人工涙液や涙の分泌を促す点眼薬、涙点プラグによる治療、まぶたのマッサージや温罨法などが有効です。重症の場合には、軟膏や自己血清点眼、上下眼瞼縫合術が行われることもあります。
日常生活では、まばたきを意識的に増やし、加湿器を利用するなどの対策が重要です。ドライアイと似た症状を示す疾患には、シェーグレン症候群、眼類天疱瘡、顔面神経麻痺による兎眼などがあり、正確な診断が必要です。適切な治療とケアを行うことで、症状を軽減し、快適な視生活を送ることができます。