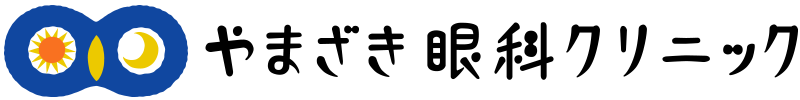糖尿病網膜症
糖尿病網膜症について
糖尿病網膜症(とうにょうびょうもうまくしょう)は、糖尿病の長期的な合併症の一つで、血糖値の高い血流にさらされた網膜の毛細血管が障害を受け、視力の低下を引き起こす疾患です。初期にはほとんど自覚症状がなく、気づいたときには病気がかなり進行していることが多いため、症状がなくても半年~1年に1回の定期的な眼科検診が非常に重要です。適切な時期に治療を受けることで、重症化を防ぎ、目の機能を長持ちさせることができます。
糖尿病網膜症の原因
糖尿病網膜症の発症頻度
日本では、糖尿病患者は約1,000万人以上いると推定されており、そのうち約30%が糖尿病網膜症を発症するといわれています(2025年現在)。糖尿病の罹病期間が長くなるほど発症率が高まり、10年以上経過すると約半数が何らかの網膜の異常を伴うとされています。特に、血糖コントロールが不十分な場合や、高血圧・脂質異常症・喫煙といった危険因子を持っている場合には、病気の進行が早くなる傾向があります。
病態の進行
高血糖が持続すると、網膜の毛細血管が障害を受け、血管壁がもろくなったり、血管が詰まったりすることで、以下のような異常が生じます。
眼底出血
血管が破れて、血液が網膜内に漏れます。初期には小さな点状出血が見られますが、進行すると大きな出血を伴うことがあります。
硬性白斑
血液中の蛋白成分が漏れ、白っぽい斑点として眼底に現れます。症状はないことが多いですが、網膜の中心である黄斑部に蓄積した場合には難治性の視力低下を生じることがあります。血管の出血している部位の周囲に輪状に広がって観察されることもあります。
軟性白斑
網膜の虚血(酸素不足)の影響で、網膜の神経細胞が障害され、白くぼやけた斑点として現れます。これは網膜の酸素供給が不足しているサインであり、病気の進行を示します。
血流障害と新生血管
毛細血管が詰まると、網膜は酸素不足を補おうとして、新たな血管(新生血管)を作ります。しかし、新生血管は通常の血管とは異なり、壁が薄くてもろいため、簡単に破れて出血を起こします。これにより硝子体出血が生じ、急激な視力低下を引き起こすことがあります。また、網膜から目の中心に向かって伸びてきた新生血管から増殖膜と呼ばれる膜状の組織が発達することがあります。増殖膜は傷を治そうとするからだの働きの一部ですが、この膜が時間とともに収縮するなどの変化をして縮むような力が加わると網膜が強く引っ張られることがあり、これによって牽引性網膜剥離と呼ばれる状態が生じることがあります。網膜は、カメラでいう「フィルム」のような役割を持っており、目の奥で光を感じる大切な部分です。しかし、牽引性網膜剥離が起こると、この網膜が本来の位置から引きはがされてしまい、光を正常に感じることができなくなります。すると、視界の一部が暗くなったり、視力が急に低下したりすることがあります。特に黄斑(おうはん)と呼ばれる、ものを見る中心部分に剥離が及ぶと、視力が著しく低下し、治療をしても視力が元に戻りにくくなることがあります。
また糖尿病網膜症が悪化すると、隅角(ぐうかく)と呼ばれる目の中の水(房水)が流れ出る部分にも新生血管が広がることがあります。隅角は、目の中の水の排水口となっており、目の圧力(眼圧)を調整する大切な部分ですが、新生血管がここにできると、正常な房水の流れが妨げられ、眼圧が異常に上昇してしまうことがあります。目の重みや圧迫感を感じたり、網膜や視神経が高い眼圧にさらされることで障害を受け、放置すると短期間で失明につながる可能性もあります。これが「血管新生緑内障(けっかんしんせいりょくないしょう)」と呼ばれる状態です。
その他
糖尿病網膜症の影響が視神経にも及ぶことがあり、視神経の血管が障害されることで腫れ(乳頭腫脹)が生じ、視力低下を引き起こします。これを糖尿病性視神経乳頭腫脹と呼びます。また、糖尿病によって引き起こされる虹彩(こうさい:黒目の周りの色のついた部分)に炎症を生じることがあります。これを糖尿病性虹彩炎と呼びます。
糖尿病網膜症の症状
糖尿病網膜症の初期段階ではほとんど自覚症状がありません。しかし、進行すると次のような症状が現れます。
病期に対応した症状
1. 単純糖尿病網膜症(初期)
- 自覚症状なし(検診で発見されることが多い)。
- 血管瘤(血管の膨らみ)、点状出血、白斑が眼底に見られる。
2. 増殖前糖尿病網膜症(中期)
- 視力低下が始まることがあるが、多くの場合は軽度。
- 軟性白斑(酸素不足による網膜浮腫)、血管の狭窄や不整がみられる。
- 黄斑浮腫があると、視界の歪みやぼやけが出現。
3. 増殖糖尿病網膜症(重症)
- 硝子体出血により、突然視界が暗くなることがある。
- 視野の欠損(部分的に見えなくなる)。
- 血管新生緑内障が発生すると、眼圧が上昇し、眼痛を伴うことがある。
一般的な症状
- 視力低下:ものがぼやける、細かい文字が読みづらい。
- 飛蚊症(ひぶんしょう):目を左右に動かすと細かい影がワンテンポ遅れて動くように見える。これは硝子体出血の初期症状であることがある。
- 視野の欠損:網膜の血流障害により、視界の一部が欠ける。
- 突然の視力喪失:重度の眼底出血や網膜剥離が起こると、急激に視力が低下する。
糖尿病網膜症の治療
血糖・血圧の管理
- 一般的にはHbA1c 7.0%未満を目標(1)にするとされています。目標値は年齢や糖尿病の状態についても変わってきますが、糖尿病の治療を行うことが重要です。
(HbA1cとは、過去1〜2か月間の平均的な血糖値を示す指標です。血液中の赤血球に含まれる「ヘモグロビン」というタンパク質が、血糖と結びついた割合を示しています。) - 生活習慣の改善に加え、内科で治療されている血糖・血圧の管理を継続することが重要になります。
- 血糖値の高い期間が長いと、血糖値が改善しても血管へのダメージが残った状態となってしまい、HbA1cの値が改善しても糖尿病網膜症が改善しない場合があります。糖尿病の早期治療が網膜症の予防という観点からも重要です。
レーザー治療
汎網膜光凝固
酸素不足の網膜の一部にレーザーを当てて細胞の働きを抑えることで、「酸素を必要とする部分を減らし」、新生血管ができるのを防ぐ治療です。 これは将来の重症化を防ぐための治療であり、視力を改善するものではありませんが、適切なタイミングで行うことで、硝子体出血や網膜剥離といった深刻な合併症を予防し、視力を守ることにつながります。
抗VEGF療法
糖尿病によって目の中に異常な血管ができたり、むくみ(黄斑浮腫)が起こったりするのを防ぐために行う治療です。VEGF(ブイイージーエフ)という物質は、血管を作る働きを持っていますが、糖尿病になるとこのVEGFが過剰に増えてしまい、もろく破れやすい異常な血管ができたり、網膜が腫れたりする原因になります。抗VEGF治療では、このVEGFの働きを抑える薬を目の中に直接注射し、新生血管の増殖を防ぎ、網膜の大切な部分である黄斑の浮腫を軽減します。
この治療は効果が高い場合が多く、視力を維持したり、改善したりすることが期待できます。ただし、一度の注射で完治するわけではなく、効果を維持するためには定期的に繰り返し注射を受ける必要があります。人によっては数か月ごとに治療を続ける必要があり、治療の間隔や回数は患者さんの状態によって異なります。また、薬の効果が十分に現れない人もいて、すべての患者さんに必ず効くとは限りません。
抗VEGF治療は高価な治療であり、1回の注射に数万円の費用がかかることが一般的です。費用はかかるものの、視力を守るためにはとても重要な治療であり、適切な時期に受けることが将来の目の健康を維持するために役立ちます。
局所ステロイド療法
糖尿病が原因で長期間続く慢性的な網膜の炎症や血管の異常を抑えるために行う治療です。ステロイドには強力な抗炎症作用があり、目の周囲に直接注射することで、炎症を抑え、黄斑のむくみを軽減する効果が期待できます。ステロイドは副作用として眼圧が上がること(緑内障のリスク)や、白内障が進行しやすくなる可能性があるため、定期的な経過観察が必要になります。
この治療は、糖尿病黄斑浮腫に対して抗VEGF治療が効きにくい場合や、慢性的な炎症が関与している患者さんに有効とされています。
硝子体手術
重度の硝子体出血や網膜剥離に対しては専門施設で手術加療が行われます。
まとめ
糖尿病網膜症は、初期には無症状で気づきにくく、適切な時期に治療を受けることで重症化を防ぐことができます。気が付かない間に進行し、硝子体出血や血管新生緑内障といった重篤な合併症を引き起こすため、症状がなくても定期的な眼科検診が重要です。
糖尿病のコントロールは眼だけでなく全身の健康にも関わるため、内科との連携を図りながら、網膜症の進行を遅らせることが大切です。
参考文献:糖尿病治療ガイドライン2024, 南江堂.