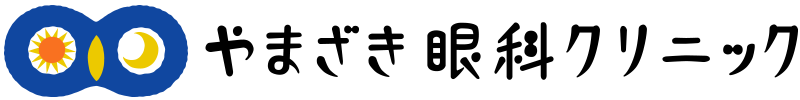コンタクトレンズ関連
原因
近年、日本では近視の人口が増えています。特に、スマートフォンやパソコンの使用時間が長くなったことや、屋外で過ごす時間が短くなったことが関係していると考えられています。そのため、視力を矯正するためにコンタクトレンズを使用する人も増えてきました。 コンタクトレンズは便利ですが、間違った使い方をすると目の健康に悪影響を及ぼすことがあります。特に、コンタクトレンズを長時間装用したり、不適切な管理をしたりすると、目の感染症や炎症のリスクが高くなります。
また、「コンタクトをつけると視力がどんどん悪くなるのでは?」と心配する方もいますが、基本的にコンタクトレンズそのものが近視を進行させることはありません。ただし、目に合っていないコンタクトを使い続けると、目に負担がかかり、視力が悪くなることがあります。そのため、適切なレンズを選び、正しく使うことが大切です。
コンタクトレンズの
種類と特徴
コンタクトレンズにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズの2つについて説明します。
ハードコンタクトレンズ
ハードコンタクトレンズの特徴
- 硬い素材でできた小さめのレンズ。
- 角膜の表面に涙の層を挟んで浮くような形で装用する。
- 1枚のレンズを長期間(数年単位)使うことができる。
酸素透過性
- ハードレンズは酸素をよく通すものが多い。
- 直接涙が流れ込みやすいため、酸素不足になりにくい。
角膜乱視の矯正効果
- 角膜乱視のある人にも向いている。→レンズが涙の層を作り、目の表面をなめらかに補正するから。
向いている人
- 乱視が強い人
- 酸素不足による目のトラブルを防ぎたい人
ソフトコンタクトレンズ
ソフトコンタクトレンズの特徴
- やわらかい素材でできたレンズ。
- 水分を含んでいるため、目になじみやすい。
- 1日使い捨てタイプや2週間タイプなどがあり、手軽に使える。
酸素透過性
- ハードレンズよりも酸素透過性が低いが、最近は酸素を通しやすい素材もある。
- 長時間の装用には注意が必要。
角膜乱視の矯正効果
- 軽度の乱視は矯正できるが、乱視が強い人には向いていない。
向いている人
- スポーツをする人(ズレにくいため)
- 初めてコンタクトを使う人
- 短時間の装用を考えている人(使い捨てレンズ)
まとめ
| レンズの種類 | 酸素透過性 | 角膜乱視の矯正効果 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| ハードコンタクトレンズ | 高い | 強い (乱視にも対応) |
乱視が強い人 |
| ソフトコンタクトレンズ | 中程度 (最近は高酸素透過レンズもあり) |
軽度の乱視なら対応可 | 初めての人 スポーツをする人 |
症状
コンタクトレンズによって起こる目のトラブルには、以下のような症状があります。
- 目の充血(白目が赤くなる)
- 目がゴロゴロする、異物感がある
- かゆみや痛み
- 涙が止まらない
- 視界がぼやける、かすむ
- 光がまぶしく感じる
特に、強い痛みや視力の低下がある場合は、眼科受診が必要と考えられます。
検査
コンタクトレンズによる目のトラブルが疑われる場合、眼科では以下のような検査を行います。
1. 視力検査
視力の低下があるかを確認します。
2. 細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)
特殊な顕微鏡を使って角膜(黒目の表面)や結膜(白目)を詳しく観察します。
3. フルオレセイン染色検査
目の表面の傷を確認するために、専用の薬を使って検査します。
4. 細菌やアメーバの検査
感染が疑われる場合は、目の分泌物を採取して病原体を調べます。
コンタクトレンズ装用に伴う合併症
コンタクトレンズ関連の合併症として、以下のような疾患があります。
1. 角膜感染症(細菌・真菌・アメーバ)
- 緑膿菌感染症
急速に進行し、角膜穿孔を引き起こすリスクがある。 - アカントアメーバ角膜炎
初期では診断が難しく、目の検査結果と比較して痛みが強いことが多い。難治性で失明のリスクもある。 - 真菌性角膜炎
汚れたレンズが原因となることがあり、難治性のものあり。
2. 角膜内皮細胞減少
- 酸素透過性の低いレンズの長時間使用により、角膜の内皮細胞が減少し、角膜浮腫を引き起こすことがある。
- 重症化すると、角膜移植が必要になるケースもある。
3. 角膜血管新生
- 酸素不足の状態が続くことで、角膜内に異常な血管が伸びてくる現象。
- 進行すると視力低下やコンタクトの位置ずれの原因となることがある。
4. 巨大乳頭結膜炎(GPC)
- コンタクトレンズの長期使用により、まぶたの裏に大きな乳頭ができる疾患。
- かゆみや異物感が強くなり、コンタクト装用が困難になる。
5. ドライアイの悪化
- コンタクトレンズにより、慢性的なドライアイを引き起こすことがある。
- 角膜障害や視力低下につながることもある。
6. 角膜潰瘍
- 目の充血、痛み、目ヤニで発症。
- 角膜の深部まで炎症が及ぶと、治療後も角膜混濁が残って視力低下が残ってしまうことがある。
- 最重症例では角膜穿孔(穴が開く)し、緊急対応が必要になることがある。角膜穿孔の場合には、目の中の水(房水)が漏れ出てしまうため、温かい涙がたくさん流れ出るように感じる。
生活上の注意点
長時間の連続装用を避ける
コンタクトをつけたまま寝たり、1日中装用したりすることは特殊な場合を除いて目に負担をかけるため、控えましょう。
定期的に眼科で検査を受ける
目に異常がなくても、少なくとも年に1回程度は検査を受けることが勧められます。
レンズの洗浄をしっかり行う
使い捨てレンズ以外:専用の洗浄液を使用し、ヌルヌルした部分が取れるようにコンタクトレンズを洗いましょう。コンタクトレンズケースが細菌やアメーバの温床となることがあるため、毎回新しい保存液で満たし、液体の使いまわしをしないことが重要です。利用していない時にはふたを開けておき、乾燥させることも有効です。感染を防ぐために、定期的にレンズケースを交換することも推奨されています。
カラーコンタクトレンズの使用を最小限にする
カラーコンタクトは以前は酸素透過性が低く、目に負担がかかるとされていました。最近は、酸素透過性の高い種類も出てきており、目の負担がそれほど大きくならないものも出てきています。カラーコンタクトレンズの方が、そうでないコンタクトレンズより感染症などの症状を生じやすかったという報告もなされており、注意が必要です。
調子が悪いときはすぐに外す
目に違和感があるときは無理せず、すぐにレンズを外して目を休ませて下さい。
鑑別疾患
コンタクトレンズ関連の疾患と区別が必要な疾患
コンタクトレンズのトラブルと似た症状が出る病気もあります。
アレルギー性結膜炎
花粉やホコリなどが原因で目のかゆみや充血を引き起こす病気です。涙が多くなったり、まぶたの裏にブツブツができることもあります。コンタクトレンズを装用すると症状が悪化することがあるため、レンズを洗浄しアレルギー物質を眼に接触させないことが大切です。
ドライアイ
涙の量が少なかったり、涙がすぐに蒸発したりすることで目が乾燥し、ゴロゴロした違和感やかゆみ、かすみ目などを引き起こす病気です。コンタクトレンズを長時間つけると、症状が悪化することがあります。目を休めたり、目薬を使ったりすることで症状を軽減できます。
角膜ヘルペス
単純ヘルペスウイルス(HSV)が角膜に感染して起こる病気です。症状として、目の充血や痛み、視力の低下がみられ、放置すると角膜に傷がつき視力が悪くなることもあります。再発しやすい病気で、長期間の治療が必要になることがあります。
麦粒腫(ばくりゅうしゅ)・霰粒腫(さんりゅうしゅ)
麦粒腫はまぶたの脂を出す腺が細菌感染を起こし、赤く腫れて痛みを伴う病気です。霰粒腫は、同じ脂の腺が詰まり、炎症が慢性化してしこりができる病気です。コンタクトレンズの汚れや不適切な装用が原因で、目をこすったり清潔にしないと細菌が繁殖しやすくなり、これらの病気のリスクが高まることがあります。
まとめ
日本では近視の人口が増え、それに伴いコンタクトレンズの使用者も増えています。コンタクトレンズにはハードレンズとソフトレンズがあり、それぞれ特徴が異なります。ハードレンズは酸素をよく通し、乱視の矯正に向いているが慣れるまで違和感がある場合があります。一方、ソフトレンズは装用感が良くスポーツ向きだが、酸素透過性が低いものもあり、長時間の装用には注意が必要です。コンタクトレンズの使用に伴い、感染症やドライアイ、角膜のトラブルが生じることがあります。調子の悪い時には無理せず、コンタクトを外して目を休ませるのも重要です。