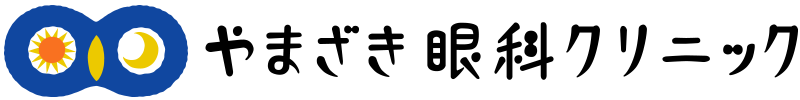加齢黄斑変性(AMD)
加齢黄斑変性(AMD)
加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい、AMD)は、目の「黄斑(おうはん)」という部分が傷んでしまう病気です。黄斑は、物を見るときにとても大切な働きをする場所で、ここが悪くなると視力(ものの見え方)が低下したり、ものがゆがんで見えたりします。特に50歳以上の方に多く見られ、日本でも高齢化に伴い患者数が増加しています。
加齢黄斑変性の原因
加齢黄斑変性(AMD)は、高齢者の視力低下の主な原因の一つです。特に50歳以上の人に多く見られ、日本における患者数も増加傾向にあります。
主な原因とリスク要因
加齢
年齢が高くなるほど発症リスクが上昇します。
遺伝的要因
家族歴があると発症しやすいとされています。
喫煙
喫煙者は非喫煙者に比べて発症リスクが2~3倍高いと報告(1)されています。
食生活
長期間の曝露が網膜のダメージにつながる可能性があります。
紫外線
抗酸化作用のある栄養素(ルテイン・ゼアキサンチンなど)の不足が影響します。
生活習慣病
高血圧や動脈硬化、糖尿病などがリスクを高めると考えられています。
加齢黄斑変性の症状
AMDは初期段階では自覚症状が少ないことがありますが、進行すると視力低下を引き起こします。
- 視界のゆがみ(変視症):直線が波打つように見える
- 視野の中心が暗くなる(中心暗点)
- 視力低下:特に細かい文字が読みにくくなる
- 色の識別が難しくなる
加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい、AMD)は、目の「黄斑(おうはん)」という部分が傷んでしまう病気です。黄斑は、物を見るときにとても大切な働きをする場所で、ここが悪くなると視力(ものの見え方)が低下したり、ものがゆがんで見えたりします。 AMDには、大きく分けて「萎縮型(いしゅくがた)」と「滲出型(しんしゅつがた)」の2つのタイプがあります。
1. 萎縮型AMD(いしゅくがた 加齢黄斑変性)
萎縮型AMDの特徴
- 進行がゆっくり
- 黄斑の細胞が少しずつ減っていくことで、視力が下がる
- 出血やむくみ(腫れ)は起こらない
- ものがかすんで見えたり、暗く見えたりする
- 重症になると、中心が見えなくなることがある
萎縮型AMDの治療・予防
- 完全な治療法はまだない
- ビタミンやミネラル(AREDS2サプリメント)をとることで進行を遅らせることができるとされる
- 目を紫外線から守る(サングラスをかけるなど)のもある程度は有効とされる
2. 滲出型AMD(しんしゅつがた 加齢黄斑変性)
滲出型AMDの特徴
- 進行が早く、急に視力が落ちることがある
- 血管が異常に増えて、出血やむくみ(液体が漏れること)が起こる
- ものがゆがんで見える(まっすぐな線が波打って見える)
- 進行すると視野の中心が見えなくなることもある
目の中で何が起きているの?
- 異常な血管(しんせいけっかん)が発生する
- 血管がもろく、血液や水分が漏れやすい
- 網膜(ものを見る大事な神経の層)が腫れてしまう
- ひどくなると、黄斑の組織が傷んでしまい、視力が低下してしまう
滲出型AMDの種類
滲出型は、異常な血管がどこにあるかで3つのタイプに分かれます。
| タイプ | 異常な血管の場所 | 特徴 |
|---|---|---|
| タイプ1 | 網膜色素上皮(もうまくしきそじょうひ)という層の下 | 進行が比較的ゆっくり |
| タイプ2 | 網膜の下(視細胞のすぐ下) | 出血やむくみがひどく、進行が早い |
| タイプ3(RAP) | 網膜の中に異常な血管ができ、広がっていく | 両目に起こりやすく、進行が早い |
抗VEGF薬(こうVEGFやく)という注射で治療する
- VEGF(ブイイージーエフ)は、新しい血管を作る働きをする物質であり、体にとっては重要なものだが、AMDでは、VEGFが異常に増え新生血管ができすぎてしまう。その結果、血管がもろくなって出血やむくみが起こる。
- これを抑える薬を目の中に注射する
- 抗VEGF薬の注射は1度注射しても効果がずっと続くわけではない。通常最初の3ヶ月は毎月注射することが多く、その後は効果を見ながら1~3ヶ月ごとに追加の注射が必要になる場合が多い。
抗VEGF薬では改善が乏しい場合に、レーザー治療や光線力学療法(PDT:光と薬を組み合わせて、異常な血管だけを狙って治療する方法)も検討される。
萎縮型と滲出型の違い
| 萎縮型(いしゅくがた) | 滲出型(しんしゅつがた) | |
|---|---|---|
| 進行のスピード | ゆっくり | 早い |
| 出血・むくみ | なし | あり |
| 視力低下 | じわじわ進む | 急に悪くなることがある |
| 治療法 | ビタミン・ミネラルなどで予防 | 抗VEGF薬の注射が有効 |
加齢黄斑変性の検査
加齢黄斑変性の診断には、以下の検査が行われます。
主な検査方法
- 視力検査・アムスラーチャート:視野のゆがみを確認
- 眼底検査(OCT:光干渉断層計):網膜の断層画像を撮影し、異常を評価
- OCTアンギオグラフィー(OCTA):非侵襲的に新生血管を検出
- 蛍光眼底造影(FA)・インドシアニングリーン蛍光造影(ICGA):新生血管の有無を確認
加齢黄斑変性の治療
AMDの治療法は病期やタイプによって異なります。
滲出型(新生血管型)の治療
- 抗VEGF療法(硝子体注射):新生血管の成長を抑える薬(アフリベルセプト、ラニビズマブ、ブロルシズマブ、ファリシマブなど)を注射
- 注射は1回では終わらず、最初の3ヶ月は毎月注射を行い、その後は症状に合わせて1~3ヶ月毎に注射されるケースが多いです。
- レーザー治療(光線力学療法:PDT):選択的に新生血管を閉塞させる
萎縮型(地図状萎縮型)の治療
現時点で有効な治療法は確立されていませんが、進行を遅らせるための研究が進められています。(2025年現在)
生活上の注意点
日常生活で気をつけること
- 禁煙:喫煙は最大のリスク因子の一つ
- 食生活の改善:緑黄色野菜や魚(オメガ3脂肪酸)を積極的に摂取
- 紫外線対策:サングラスや帽子で目を保護
- アムスラーチャートでセルフチェック:視界のゆがみがないか確認
鑑別疾患
加齢黄斑変性と区別が必要な疾患
中心性漿液性網脈絡膜症(CSC)
目の黄斑(ものを見る大事な部分)の下に水がたまる病気です。ストレスやホルモンの影響で血管がもろくなり、水分が漏れやすくなることが原因と考えられています。視界の中心がぼやけたり、ものがゆがんで見えたりすることがありますが、多くの場合は自然に治ることが多いです。働き盛りの30~50代の男性に多い疾患です。治らない場合は、レーザー治療や薬で対処することがあります。
黄斑円孔
目の黄斑(ものを見る大事な部分)に穴が開いてしまう病気です。視界の中心がぼやけたり、黒く抜けたりし、細かいものが見えにくくなります。自然に治ることは少なく、手術(硝子体手術)で穴をふさぐ治療が必要です。
糖尿病黄斑浮腫(DME)
糖尿病が原因で目の黄斑に水分がたまり、視力が低下する病気です。視界がぼやけたり線がゆがんで見えたりします。
網膜静脈閉塞症(RVO)
目の血管(静脈)が詰まり、血流が悪くなって出血やむくみが起こる病気です。視界がぼやけたり、部分的に暗くなったりすることがあり、重症になると視力が大きく低下します。
近視性黄斑変性(mCNV)
強い近視(強度近視)が原因で、黄斑に異常な血管(新生血管)ができる病気です。出血やむくみが起こり、ものがゆがんで見えたり、視力が急に下がることがあります。
まとめ
加齢黄斑変性(AMD)は、目の黄斑が傷んで視力が低下する病気で、特に50歳以上の高齢者に多く見られます。原因として、加齢、遺伝、喫煙、食生活、紫外線、高血圧などが関与します。AMDには進行が遅い萎縮型と、異常な血管が増えて視力が急激に悪化する滲出型の2種類があります。
症状としては、視界のゆがみ(変視症)、中心が暗く見える(中心暗点)、視力低下などが挙げられます。診断には、視力検査、眼底検査、OCT(光干渉断層計)などが用いられます。滲出型AMDの治療は、抗VEGF注射が基本で、必要に応じてレーザー治療や光線力学療法も併用されます。萎縮型には有効な治療法はまだ確立されていませんが、進行を抑えるための研究が進められています。
予防として、禁煙、バランスの取れた食事、紫外線対策、定期的な目の検査が重要です。また、AMDと似た症状を持つ疾患(中心性漿液性網脈絡膜症、糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症など)との鑑別も必要です。
参考文献:1 Br J Ophthalmol. 2006 Jan;90(1):75-80.