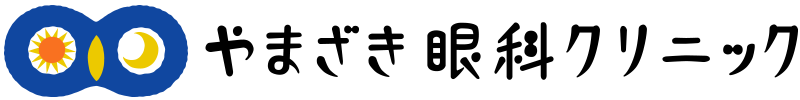弱視
はじめに
〜視覚の発達と感受性期〜
視覚は出生後から徐々に発達していくものであり、生後すぐの赤ちゃんの視力は低い状態にあるとされています。その後、光を目や脳を通して感じていくことで、次第に視力が向上していきます。この視覚の発達には「感受性期」と呼ばれる重要な期間があり、この時期に適切な視覚刺激を受けることで視力が正常に発達します。
視力の発達は、1歳で0.1、2歳で0.5、3歳で1.0に到達するとされています。(乳幼児での視力測定は難しく、報告によって多少ばらつきはあります)物を目で追いかける追視は、生後1ヶ月頃からみられ、3か月健診でも確認されています。
視力の感受性期は一般に生後数ヶ月から7〜8歳頃までとされており、この期間に十分な光の刺激が網膜に得られないと、脳の視覚野が適切に発達せず、その後の視力回復が難しくなることがあります。このように、視覚の発達には環境からの刺激が不可欠であり、感受性期に異常があると視機能の成熟が妨げられ、視力の低下を引き起こすことがあります。
弱視とは
弱視の定義
弱視とは、眼球自体には明らかな異常がないにもかかわらず、視力が十分に発達しない状態を指します。通常、矯正視力が1.0未満であり、適切な眼鏡やコンタクトレンズを装用しても視力の改善が見られない場合に診断されます。
弱視の有病率は、国内では3歳児健診とその後の診察の結果から0.6%(1000人に6人)程度とされています。
弱視の分類
弱視にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる原因によって引き起こされます。
1. 屈折異常弱視
- 強い遠視や乱視があると、網膜に鮮明な像を結ぶことができず、視力が発達しません。
- 両眼に強い屈折異常がある場合(両眼屈折異常弱視)や、一方の目だけに屈折異常がある場合(不同視弱視)があります。
2. 斜視弱視
- 斜視により片目の視線がずれることで、両眼で物を見る機能(両眼視機能)が発達せず、使われない方の眼の視力が低下します。
3. 形態覚遮断弱視
- 先天白内障や眼瞼下垂など、眼への視覚刺激が物理的に遮られることで生じる弱視です。
- 網膜に全く光が当たらない場合は、早く視力発達障害が完成してしまうため、生後早期(片眼の場合には生後8週まで、両眼の場合には生後12週まで)に光が網膜に届くように治療を行わないと、視力の発達が著しく制限されるとされています。
弱視の検査
診断には以下の検査が行われます。
視力検査
乳幼児の場合、視力検査には専用の視力表や行動を観察することで行います。一般的な視力検査の方法としては以下があります。
- ランドルト環視力表(一般的な視力検査)
- 絵視力表(幼児向け)
- 視覚誘発電位(VEP)(視神経の反応を測定する検査)
屈折検査
- オートレフラクトメーターを用いた測定
(オートレフラクトメーターとは、目の屈折異常(近視・遠視・乱視)を測る機械です。目に赤外線の光を当てて、網膜にどのようにピントが合うかを自動で測定します。眼科や眼鏡店で、視力検査の前に使われることが多い装置です。) - アトロピンやシクロペントラートを用いた検査
(調節を麻痺させた状態での正確な屈折異常の測定。調節とは水晶体の厚みを変えて、ピントを合わせる働きのことで幼少期の子供は水晶体が柔らかいため調節力がとても強いです。本来の目のピントの合う位置を調べるために、調節を行う筋肉を目薬で麻痺させて検査を行います。アトロピンは強力な調節麻痺効果が得られますが、7日間程度1日2,3回の点眼をしてから測定します。効果は3週間程度継続します。)
眼位の検査
- 正面からペンライトの光を当てて、黒目の反射の位置を確認したり、特殊な機械で網膜の反射と黒目の反射の関係をチェックしたりします。眼球の位置にズレがないかどうかをチェックします。
両眼視機能検査
- ステレオテスト(両眼の立体視機能を測定。特殊なメガネをかけて、絵や図形が浮き出て見えるかを確認します。両目の協調が悪いと、立体的に見えず弱視や斜視の可能性があることがわかります)
- カバーテスト(目のズレ(斜視)があるかどうかを調べる検査です)
- 片目を隠す(カバーテスト)
まず、どちらかの目(優位眼=よく使う目)を隠します。このとき、もう片方の目(非優位眼)がズレていた場合、ピタッと元の位置に動くことがあります。これは、今までサボっていた目が、ちゃんと見ようとして動いた証拠です。 - 隠した目を外す(アンカバーテスト)
次に、隠していた優位眼を出します。すると、再び優位眼が見ようとして、非優位眼がズレることがあります。この動きによって、斜視の有無を判断します。
前眼部・中間透光体・眼底検査
- 視力低下の原因となるような病気がないか確認します。弱視では目そのものに問題がなく、刺激が足りないことで見る機能が発達しない事が原因ですが、一見分かりにくい病気が原因の場合があります。
治療
治療は病状の進行度や症状に応じて選択されます。
1. アイパッチ治療
弱視の治療法として最も一般的なのが「アイパッチ療法」です。これは健眼(視力の良い方の眼)を遮蔽することで、弱視眼を積極的に使わせ、視力の発達を促す方法です。視力0.2以下の弱視では、6時間以上、視力0.2から0.5の弱視では2時間以上、健眼遮閉を行います。
2. 屈折矯正
眼鏡を用いて、正確な視覚刺激を与えることが基本となります。
3. アトロピン療法
アイパッチが難しい場合、アトロピン点眼を健眼に使用して調節を抑えて健康な方の目をわざと見えにくくすることで、弱視眼の使用を促す方法もあります。
4. 手術治療
網膜までの光を遮るものがある場合、弱視治療として緊急度が高い状態です。先天白内障であれば、片眼の白内障であれば生後8週、両眼の白内障であれば、生後12週までに治療しないと視力発達障害が大きいとされています。眼瞼下垂による障害は、子供自身が顔の向きを調整することで目に光が入ること多く、視力の発達に問題のないケースが多いです。重度の眼瞼下垂では、テーピングで上まぶたを挙げたり、手術が行われる場合があります。
5. 成長段階による治療の変化
乳幼児期(0〜2歳)
- 遮蔽弱視や形態覚遮断弱視では、できるだけ早期の治療(手術など)が必要。
- 眼鏡装用の開始。
幼児期(3〜5歳)
- 視力検査が可能となるため、弱視の診断がつきやすい。
- アイパッチ療法やアトロピン療法を行う。
学童期(6〜12歳)
- 治療効果が出やすい最後の時期。
13歳以降
- 感受性期が終了し、治療に反応しにくくなるため、視力の改善が困難になる。
- 未治療の場合には多少反応する場合もある。
治療の終了について
- 治療を突然終了すると弱視が再発する場合があります。特に長時間アイパッチを行っていた場合に再発率が高いです。2年以上再発がない場合には、弱視が再発することはないとされています。
- 視力が伸びてきたら徐々にアイパッチの時間を短くしていきます。
6. 生活上の注意点
- 早期発見・早期治療:3歳児健診や就学前健診して視力が伸びていない状態を早めに見つけます。
- 眼鏡の適切な装用:目の屈折の状態に合わせて、網膜にピントの合った光が当たるようにします。
まとめ
視覚は出生後から発達し、特に7〜8歳頃までの「感受性期」に適切な刺激を受けることで正常に発達します。弱視とは、眼に明らかな異常がないにもかかわらず視力が発達しない状態であり、矯正しても視力が1.0未満となる場合に診断されます。国内では、3歳児健診後精査で約0.6%の有病率が報告されています。
弱視には、屈折異常弱視、斜視弱視、形態覚遮断弱視などの種類があり、それぞれ異なる原因で発症します。診断には、視力検査や屈折検査、眼位検査、両眼視機能検査などが用いられます。治療法としては、アイパッチ療法、眼鏡矯正、アトロピン療法、手術などがあり、特に感受性期内の治療が重要とされています。
治療効果は年齢によって異なり、6〜12歳が最後の治療可能な時期とされ、13歳以降は視力の改善が難しくなります。また、治療の終了は慎重に行い、急な中止は再発のリスクを伴います。生活面では、早期発見・治療、適切な眼鏡の装用が重要です。